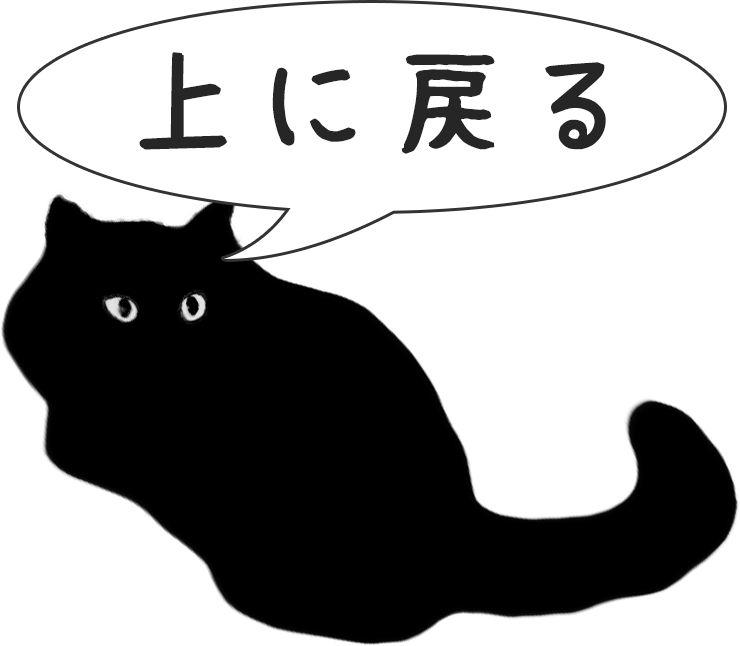赤毛のアンの子どもたち
お帰りなさい、ウォルター ―赤毛のアンの子どもたち―
1 アンの生きた時代
「あまちゃん」「ごちそうさん」に続くNHKの朝ドラ「花子とアン」は、赤毛のアン」を翻訳した村岡花子の話です。おおむね好評なスタートを切っているようで、主人公の花子が田舎から都会のお嬢様学校に出てくるまでの話の中に、「赤毛のアン」のさまざまな場面やエピソードが、それとなく重ねあわされている趣向も、話題を呼んでいます。
この趣向には批判的な意見もありますが、私が苦笑しつつ受け入れてしまうのは、小学校時代に読んで、それ以後ずっと愛読した「赤毛のアン」とその続編に描かれた美しいカナダの自然や人々の生活を、九州は大分県の国東半島に近い田舎にあった私の家やその周辺の風景と、いつも重ねあわせて想像していた私自身を思い出してしまうからです。
田舎で村医者をしていた祖父の家で、祖父母と離婚した母と四人家族で私は暮らしていました。若いお手伝いさんや看護婦さんも同居していました。広い庭には大きな木や石灯籠や庭石があり、家の横には川が流れて、向こう岸には村の神社がありました。川の土手をさかのぼって行くと、田んぼが広がり、春にはすみれや菜の花やれんげやたんぽぽが咲き乱れました。私にとってアンの住むプリンス・エドワード島の風景は、いつもそれらと重なっていました。多くの読者がそのように、自分の周囲の景色と、アンの世界をどこかでとけあわせて味わっていたのだと思います。
「赤毛のアン」はアニメや映画や舞台に何度もなっていて、ご存じの方も多いでしょう。カナダのプリンス・エドワード島を舞台に、マシュウとマリラという独身の兄妹に孤児院から引き取られた、赤毛でそばかすのあるやせっぽちの少女アン・シャーリーの物語で、空想好きでおしゃべりな彼女がさまざまな人々と触れ合いながら成長して行く様子や、カナダの美しい風景、お菓子や料理をはじめとした家庭生活の楽しさが多くの読者をひきつけて来ました。
「赤毛のアン」(新潮文庫)には続編があり、地元の学校の先生になった後、大学に進んだ彼女は、やがて離れた町で小さい学校の校長になり、その後幼なじみのギルバート・ブライスと結婚して静かな港町で医師である夫を支えるよき妻として多くの子どもを育てます。「アンの青春」「アンの愛情」「アンの幸福」「アンの夢の家」「炉辺荘のアン」「虹の谷のアン」「アンの娘リラ」などに、それらの日々が描かれています。新潮文庫のアン・シリーズには、この他に「アンの友達」「アンをめぐる人々」の二冊がありますが、これはアンの周辺の人々の話で、彼女はほとんど登場しません。
今回お話しするのは、その中の最後の一冊「アンの娘リラ」についてです。
「アン」の話を愛読している人は多いでしょうが、「いつごろの話と思いますか?」と聞かれて、とっさに答えられる人は少ないかもしれません。「アンの娘リラ」は、それがはっきりわかるという点で、他の作品と大きく異なっています。この話の主人公はアンの末娘のリラで、アンは彼女をとりまく家族の一人として描かれています。そして、作品に描かれる時代は、第一次世界大戦が始まって、終わるまでの数年間なのです。それまでのシリーズで、幸福に静かに暮らしていたおなじみの一家が、戦時下でどのように生きたのかが、この作品には描かれています。
私は昭和二十一年生まれで戦争を知りません。でも戦争を題材とした小説は子どもの頃から多く読みました。アンの一家と同じような幸福で平和な家族が戦争によって苦しむ小説も、ドラ・ド・ヨング「あらしの前」「あらしの後」をはじめとして、いくつも読みました。ただ、それらの小説と「アンの娘リラ」がちがっていたのは、アンの一家もその周囲の人たちも、カナダが参戦したこの戦いを、ちょうどかつての太平洋戦争の時に日本のほとんどの家族がそうであったように、全面的に支援し、勝利を願っていたことでした。
たしかにオールコック「若草物語」やムサトフ「こぐま星座」などの小説にも、戦争を肯定し自分の国の戦いを心から支援する家族や子どもたちは登場します。しかし、それは話の中心ではありません。「アンの娘リラ」は、全編がけなげに銃後を支えた女性たちの物語、彼女たちが戦地に送り出して帰りを待った男性たちの物語でした。
私が育った時代は不思議な時代でした。田舎で育った私の周囲では戦後の民主主義や平和教育がまだあまり根付いておらず、学校では先生たちが戦地での手柄話を授業で面白おかしく話して生徒に人気がありましたし、村の祭りなどで酒を飲むと普通のおじさんたちが中国人を残酷に殺した話をこれまた普通に話していました。さすがに子どもの前では話しませんでしたから私は後で母から聞いたのですが、そんな母は近年の、中国での日本軍の残虐行為はあったかなかったかという議論を聞くたび、「だって、○○さんも◇◇さんも話してたのに」と納得できない顔をしていたものです。
日常の庶民の生活の中では、そんなことが問題にもならなかった一方で、印刷物や公共の場では戦争につながるあらゆる動きが強く否定されていました。大人の本や雑誌を読み漁っていた幼い私は、まるでアン・シャーリーが現実から逃避して本の世界に逃げ込むように、そういう思想に染まったし、戦争には絶対反対で、もしも日本が再び戦争に加わろうとしたら自分は必ず食い止めようと、子ども心に誓っていました。
時々私は、今ネトウヨと言われる若い人たちが、平和憲法や東京裁判を強く攻撃し否定するのは、そういうものに象徴される日本の戦後が無条件に正しいと、強く教えられる教育の場やマスメディアに対する疑問や反発、それと反対のものにあこがれる冒険心もあるのだとしたら、昔の私があらゆる戦争への絶対否定や暴力的なものを含む愛国心への激しい反発に走ったのと、どこか似ているところはないのかと、ややこしい疑問を抱くのです。
そんな当時の私にとって、「アンの娘リラ」の描いた世界は衝撃でした。アンをはじめとする登場人物のすべては私が現実生活での友だちや家族と同じ、もしかしたらそれ以上に、よく知っている、親しい、愛する人たちでした。その人たちが別に変わったわけではなく狂ったわけではなく、いかにもその人たちらしく、どこまでもその人たちらしいままで、戦争に協力し、敵を憎み、勝とうと望んで、大切なものを犠牲にしているのです。「こういうことをしてはいけない」と、たくさんの本から私が学び信じた、そういうまちがったことのすべてを、他ならぬアンたちがやっているのを、まざまざと私は目にしました。
2 西部戦線の向こう側
もしも私が、アンたちがこれだけ勝利を祈っている戦争を少しでも正しいと信じられたら、彼女たちと同じように敵を憎むことができたら、少しはよかったのかもしれません。さまざまな文学作品を読む中で、当時中学生だった私も少しずつ「正しい、必要な戦争も世の中にはある」と考えるようになっていました。たとえば「ウィルヘルム・テル」が描くスイスの独立戦争、「九十三年」が描くフランス革命、「静かなるドン」が描くロシア革命、「こぐま星座」や「あらしの後」の背景にあるナチスとの戦い、「誰がために鐘は鳴る」のスペイン戦争など、否定しがたい戦いもあることを知るようになっていました。それらの戦争に描かれる「敵」は、おおむね許し難い、おぞましい、醜い存在でした。そういう「敵」が相手の戦争だと思えれば、まだ「アンの娘リラ」の世界に私は溶け込めたでしょう。
けれど、あいにく私は「アンの娘リラ」を読む前に、レマルクの「西部戦線異状なし」を読んでいました。主人公の若い学生パウル・ボイメルは兵士としてドイツ軍に参加して戦っています。パウルはもちろん、彼の小隊にいる農民出身のデテリング、古参兵のカチンスキイなども私は皆大好きでした。小説はパウルの戦死した日は「西部戦線異状なし、報告すべき件なし」と記録されたほど穏やかな日だったという記述で終わります。一人の若者の死など問題にもならないのが戦争というものなのでしょう。けれど、読者は小説全体を通して描かれるパウルの心や身体を記憶し感じますから、その喪失を現実の友人や家族のような身近さで思い知らされます。
印象的な場面は多いのですが、たとえばパウルが休暇で帰省したとき、年老いた母親は身体が悪いのに、夜、息子が寝ているベッドの足元にずっと座って息子を見守っています。
いよいよ家にいる最後の晩となった。誰もものを言う者もない。僕は早くから寝てしまった。僕は枕を摑んでわが身にひしと抱きよせ、頭を枕の中に埋めた。僕が二度とふたたびこうして羽根の蒲団にくるまって寝られるかどうか、それは誰にもわかるまい。
夜がふけてから、母は僕の部屋にはいって来た。もう僕が寝込んでしまったと思ったらしい。僕はまた寝たふりをしていた。目を覚まして、顔を見合して話をするのは、僕にはあまりに苦痛だった。
母は躰の痛みを感じては、たびたび躰を曲げたりしながら、ほとんど暁近くまで、そこに腰掛けていた。しまいにはさすがに僕もこらえきれなくなって、目を覚ましたようなふりをした。
「おっ母さん、行って寝て下さいよ。この部屋でそんなことをしていると、風邪を引きますから」
母はこう言った。
「寝るのは、わたし、まだこれからいくらでも寝られますよ」
僕は起き上がった。
「僕はこれからすぐ、戦場に行くんではないんですよ。僕はこれから四週間講習に、廠舎のほうへ行くんです。そこからたぶん日曜ぐらいには、一度ここへ来られるでしょう」
母は黙っていた。やがて静かにこうきいた。
「お前、よっぽど怖いと思ってるかい」
「思ってるもんですか、そんなこと」
「わたしお前にこれだけは言っときたいと思ってたんだよ。フランスへ行ったら、女にはようく気をおつけよ。フランスの女というものは、みんな性(たち)が良くないからね」
ああ、おっ母さん、おっ母さん、あなたのお目からは、僕はまだほんの子供でしょう…‥なぜ僕はあなたの膝にこの頭をのせて、泣くことができないんです。僕はもう一度泣きたい。泣いてもう一度機嫌をとってもらいたい。僕は大人といっても、まだまだ大きな赤ん坊にすぎない。戸棚の中には、まだ僕の短い子供ズボンがかけてあるじゃないか…‥子供という時代を離れてから、まだほんの僅かな時しかたっていない。なぜその時がもう通り過ぎてしまったのであろう。
僕はできるだけ落着いたふうをして、こう答えた。
「僕たちの隊のいるところには、女なんかいやしませんよ」
「戦争へ行っても、ようく、お前、気をつけるんだよ」
おっ母さん、おっ母さん、なぜ、僕はあなたをこの腕に抱きかかえて、一しょに死んでしまってはいけないでしょう。なぜこうも僕たちは哀れな犬なんでしょう。(新潮文庫 レマルク「西部戦線異状なし」)
アンや彼女の友人の息子たちが戦った敵はドイツ軍です。私がこよなく愛したアンの息子たちと向かい合う戦線の中にはパウルたちがいた。一方の背後にはアンの一家が、もう一方の背後にはパウルの老いた母がいた。第一次世界大戦とは、どう考えても私には、ただ、そういう戦争でしかありませんでした。
そんな私の気も知らず、「アンの娘リラ」の中で、アンもリラも、その周囲の人たちも必死で戦争を支援していました。世界の情勢に一喜一憂し、パーティーやお菓子の話をしていたように、戦争の話をしていました。しかもそれは、「アン・シリーズ」の他の作品と同様に、明るさや微笑ましさにも満ちていました。私が今でも覚えているのは、アンの家のお手伝いのスーザンがヨーロッパの政治情勢を心配して、「ギリシャのコンスタンティンの家内はドイツ人ですからね、奥さん。それで希望が持てないんですよ。わたしもまさか、ギリシャのコンスタンティンがどんな家内を持っているのか気にかけようとは思いもよりませんでしたね!」というくだりです。新聞も読まなかった素朴な働き者の中年女性が、このようにグローバルな視点を持つのが、たしかに戦争のもたらす特色でもあるのでしょう。
彼女たちのまわりに、よく日本の戦後の小説や童話に登場するような、戦争に批判的、消極的な人はいなかったのでしょうか? 実はひとりいたのです。プライアという名の男性で、丸顔で髭を生やしているので、皆は「月に頬髭」とあだ名していました。信念があるのか、もともと少し空気が読めない人なのか、彼は村の人々の熱狂に同調せず、常に「この戦争は間違っている」「ドイツが勝つかもしれない」といった発言をくり返します。村人たちは怒って彼を攻撃し、彼の家の窓ガラスに石をぶつけて割ります。アンもギルバートも、それを不愉快に思っている様子はありません。
私は幼いときから、命をかけても戦争には反対すると思っていました。けれど、そういう決意や空想の中で、戦争に反対する私を迫害し攻撃するのは、いつだって、恐ろしい醜い愚かな人々でした。アン・シャーリーとその一家、私が現実の家族や友人以上によく知っていて愛していた人たち。その人たちが「月に頬髭」に対するように私をさげすみ、拒絶し、憎む。戦争に反対するということは、そういうことなのだと、「アンの娘リラ」を読んだ私は知りました。恐ろしい不気味な相手と戦うのではなく、誰よりも親しい、大切な人たちと対決し、孤立して、戦うことなのだと、あの本を読んだとき、私は思い知らされました。淋しい、冷え冷えとした思いの中で、そのようにあきらめて、それでも反対するしかないと、覚悟を決めたと思います。
3 ルシタニア号の沈没
そんな頃、やはり中学時代でしたが私はマルタン・デュ・ガールの長編小説「チボー家の人々」を読みました。芥川賞をとった郷静子「れくいえむ」という小説では第二次大戦下の日本で二人の少女が、この小説を読みふけります。また現代の女子高生がこの本を読む、高野文子「黄色い本」という漫画もあります。フランスの名門の旧家に育つジャックとアントワーヌという兄弟が主人公で、反抗的で情熱的な弟のジャックはスイスで社会主義運動に身を投じ、第一次大戦の勃発後、両軍の兵士に「資本家の金儲けのための戦争で命を捨てるのはやめよう」と訴えるビラを飛行機からまこうとして事故死します。その戦線の両側にアンの息子たちと、パウル・ボイメルがいたのだと思うと、ジャックの行動はたとえ失敗したとしても私にとっては救いだったし希望でした。けれど、この小説が私に与えた衝撃は、ジャックの死後の兄アントワーヌの物語の中にあります。それも大抵の読者なら気にもとめない一節です。
弟とちがい理知的で冷静で堅実なエリートコースを歩いたアントワーヌは、優秀な医師になっていましたが、軍医として出征した先でドイツ軍の毒ガスを吸い込み、次第に身体を蝕まれ、死に至ります。その間に彼はさまざまな人と会うのですが、その一人にフランス政府の高官で、かつて彼の患者だったリュメルという人がいます。彼はアントワーヌに戦争や政治をめぐる裏話をいくつか語って聞かせるのですが、その中で、ドイツの潜水艦が一般人も多く乗っていたルシタニア号という英国の船を攻撃して沈没させた事件にふれて、次のように言います。
「それともまた、例のルシタニヤの撃沈にしても、結局のところきわめて正当な報復行為で、つまり、ドイツ、オーストリヤ両国で、ルシタニヤに乗っていた女子供の一万倍、二万倍の女子供を、無慈悲な封鎖によって殺したことにたいする、きわめてお手やわらかな仕返しだったということなんて? ……そうなんだ、ほんとうのことなど、めったに口に出すべきではないんだ! けしからんのは敵であり、連合国はつねに正しくなければならない!」「何をおいても必要なのは、だますということ。戦っている連中に、銃後のからくりを知らせないでおくためだけにでも! そして、銃後の連中には、前線でのおどろくべき事実を知らせないでおくためにさ!」
私はそれを目にしたとき、しばらく動けませんでした。
アンの息子は三人が出征し、その中の一人が戦死します。ウォルターという美しい優しい、すぐれた詩人でもあった青年で、今になって冷静に読むとわかるのですが、ものすごく女性の読者が好むように作られています。私もころっとひっかかって、幼い少年だった頃から彼が大好きでした。繊細で弱々しく、美しいものをこよなく愛する彼は、元気な兄やクールな弟とはちがって、戦争や戦場のすべてに強い嫌悪感と拒否感を抱き、たまたま開戦時に大病を患った後の療養中だったこともあって、すぐに志願して出征した兄や友人たちの中でひとり家にとどまっています。しかし、次第に村の人々は彼に批判の目を向けはじめ、何よりも彼自身が自分の臆病さに苦しみます。母であるアンも妹であるリラも、彼を責めはしませんが、同じように苦しみます。
ウォルターは追いつめられていたのかもしれません。きっかけを探していたのかもしれません。いずれにしろ、「人を殺す」ことを何よりも恐れていた彼が、それでも戦いに行く決意をしたのは、ルシタニア号の事件を知ったからでした。「死んだ女や子どもが冷たい水に浮かんでいる姿を思い浮かべたとき、ぼくは行かねばならないとわかった」と彼はリラに告げます。母に似た空想力と想像力の豊かさはウォルターの特徴でした。それが彼に戦争を強く嫌悪させ、それが彼に戦場へ行く決意をさせたのです。
いったん戦場に出たら、彼は誰よりも勇敢で何も恐れなかった、と兄のジェムはのちにリラに語っています。これもまた、今読めばわかりますが、初めにあれほど戦場を恐れ殺人を嫌悪した彼が、敵を許せないと思った瞬間から誰よりも勇敢な兵士になり、国や同胞や正義のために命を捧げるという設定は、この上もなく感動的で効果的で、犠牲にしたものの大きさとあいまって、戦いの崇高さを高めるものとなっています。
この戦争にそのような意義を認められなかった私に、感動や高揚はなく、ただ無条件に悲しくつらかっただけでした。けれど、ウォルターも作者のモンゴメリも、きっと心から信じて疑わなかった「ルシタニア号の悲劇」とは、そのようなものであったという政府高官の発言を読んだとき、私の虚しさも淋しさも、やり場のない怒りに変わりました。これをもしウォルターが知ったら。これをもしアンたちに知らせることができたなら。あらゆる意味で幾重にも不可能なことをその時も、それからも、何度私は夢見たでしょう。
4 残された原稿
それから長い年月がたちました。ウォルターをあんなに愛した中学生の私は、今もう八十歳近い老人です。大学生になり就職して定年を迎えた今まで、細々とではありますが、平和を守り、戦争に反対する活動をとぎらせたことはありません。その底にいつもあったのは、理屈ではなく現実の体験ではなく、読書を通じて味わった悲しみと衝撃でした。ウォルターもパウルもジャックもアントワーヌも救えなかった悔恨を私がかみしめるのは、あらゆる意味で滑稽ですが、これはやはり私の実感なのです。
ここまでの話は、これまで何度か書いたり話したりしたことがあります。でも、最近になって、この話には続きが生まれました。これは終章なのかどうなのか、私にはまだわかりませんが、ともかくそれを話しておこうと思います。
NHKのドラマになるのがきっかけになったのかもしれませんが、ごく最近、新しいアンの話が文庫本になりました。「アンの想い出の日々」というタイトルの上下二冊のこの本は、すでに亡くなった村岡花子さんの孫娘村岡美枝さんが訳しています。
この本を読んで私は、「チボー家の人々」でルシタニア号のことを読んだときと同じくらいの衝撃を受けました。それ以上かもしれませんが、質がちがうので比べられるものではありません。私ももう老齢ですから、そう簡単に泣いたり驚いたり固まったりするようなことはありません。反応が鈍くなっているということもあります。だから読んだとき、すぐにはあまり何も感じませんでした。でも、次第に、じわじわと、積もった花びらの中に身体が沈んで行くような暖かい深い喜びに満たされて、そして、ひとりでに生まれたのが、「お帰りなさい、ウォルター」という一言でした。
「アンの娘リラ」は、それまでのシリーズとは異色ですが、他の作品と同じように私は大好きです。でも、それはそれとして、私はこれを読んだとき、アンの一家ともウォルターとも進む道はちがっていくことを覚悟したし、予感しました。特に戦場に出てから勇敢な兵士になって死んで行ったウォルターは、もう私と議論することもないままにちがう世界に行ったのだと実感せざるを得ませんでした。
それが、そうではなかったと、「想い出の日々」を読んでわかったのです。
「アンの想い出の日々」の原稿をめぐる話は、いろいろと謎めいています。詳しいことは上下二冊の文庫本のあとがきに書いてありますが、この本はカナダで一九七四年に一度出版されています。しかし、その内容は原稿を大変省略したもので、原型をとどめていません。にもかかわらず、これが完成版だと思われて来ました。保存されていた原稿でやっとそのことがわかったのは、ごく最近のことです。一九六八年に亡くなった村岡花子さんも、この作品のことは知らなかったのでしょう。二〇〇九年に初めて本当の完全版が出版され、今回日本語に訳されました。
もともと最初に、この原稿が出版社にもちこまれたのは一九四二年で、作者モンゴメリの死の当日です。誰が持ち込んだかは不明です。モンゴメリは自殺したとも言われており、彼女自身が持ってきた可能性もあります。
持ち込まれた一九四二年になぜすぐ出版されなかったか、一九七四年になぜ完全な形で出版されなかったか。それも今ではわかりません。しかし、特に一九四二年の第二次世界大戦中には、この作品に強く示されている戦争への嫌悪、むしろ抗議が、出版をさせにくくしたことは確かだろうと思います。
恩田陸「麦の海に沈む果実」の中に「『赤毛のアン』を好きな女の子は、女の子っぽい子が多いと思う。可愛いものが好きで、キャーッと叫んでグループを作り、みんなでお揃いのリボンを買ったりする」とあります。やけに具体的なので、実際そういう女の子たちもいるのかもしれないと思いますが、私がアンやモンゴメリに抱く印象は、むしろ暗い孤独な激しさで、アンが登場しない短編には特にそれが強く表れていると感じます。
「アンの想い出の日々」はそういった、アンが登場しない短編と、年とったアンの家族の会話でつづられる日常風景、アンやウォルターが書いた詩などが組み合わさっています。ウォルターが死の直前に書いて、世界的に有名になったという「笛吹き」の詩は「アンの娘リラ」では名前だけだったのですが、その詩も紹介されています。
ここに収められたいくつかの短編を読んだとき、そこに登場するすさまじい悪女や死にかけた孤独な老女などの容赦ない描写に、私は「あいかわらず、やるな、モンゴメリ」と久々に思い出して、その爽快さににやりとしました。
彼女の作品には常に、鋭い冷たさと、それを焼き尽くすような熱さがあります。
これらの短編では、いやそもそも「赤毛のアン」本編でさえ、モンゴメリが描くのは決して、現実離れした空想の世界にのめりこむことの肯定ではありません。むしろ、そういった夢に没頭し埋没する人たちが、しばしばあまりにも徹底した残酷なかたちで、その夢をさまさせられる話が決して悲劇でさえもなく、生き生きと楽しげに描かれています。それは、その反対に、現実を拒否した夢を描いて守り抜いて来た人たちが、思いがけない幸運から、その夢そのものの現実を手にする、といった話が、いかに危険な賭けであり、いかにまれにしか起こらない冒険の成功であるかということも、おのずと示しているのです。ひとつまちがえば狂気と奈落の底に落ちる危険と紙一重でしか、そのような美しい夢の実現は存在しません。
アニメ「赤毛のアン」が成功したのは、夢見る少女のアンと並んで、現実的で散文的なマリラを主人公に近い存在にしていることで、それは原作がすでにそうです。「赤毛のアン」はアンとマリラの物語であり、二人がそれぞれに持つ生き方や考え方や感じ方は、どちらもモンゴメリの作品にとって重要な要素です。たとえば次のような二人のやりとりが私はとても好きでした。
「そうらしいわ」アンもしぶしぶみとめた。「なにかすばらしいことがおこると思うと、あたし、想像の翼にのってとび上がるの。それで気がついた時にはドサンと地面に落ちているのよ。でもね、マリラ、飛んでいるあいだはほんとうにすてきよ……夕日の中を舞いあがっていくようなの。ドサンと落ちても埋め合わせがつくくらいよ」
「そうかもしれないが、わたしなら、静かに歩いていきたいね。とび上がったり、ドサンと落ちたりするのはごめんだよ。けれど、人にはそれぞれの生き方があるからね。(略)」
このような夢と現実の大きな落差、と思っていたら意外な接近、という壮大とさえ言える構造も含めて、「アンの想い出の日々」は、完璧にモンゴメリの世界でアンの世界で、作品の中でも外でも長い時が流れているにもかかわらず、それ以前の作品と比べてまったく変色も失速もしてはいません。甘く、すきだらけのようでいて、ゆるやかな、決してばらけない、充実感にみちています。
老いてなお美しい愛人か友人に久しぶりにあったような満足感の中で読み進めていると、最後に近く、ウォルターが死の年に戦場で書いた「余波」という詩が出て来ました。年老いて昔戦った思い出を語るという体裁で、一人の若者、細く美しい、弟のような青年を殺した体験をつづっている詩です。そこには苦い後悔があふれ、生き残った者よりも死者の方が幸せだということばもあります。誇りも喜びもまったく見られません。まるであのパウル・ボイメルが戦争を生きのびて、年老いて書いたと言ってもおかしくはない内容です。もしかしてモンゴメリは「アンの娘リラ」を書いた後に「西部戦線異状なし」を読んだのでしょうか?
余波
Ⅰ
今や年老いた我々も かつては若かった……
美しい空の下 熱き心で闘った
沸き滾(たぎ)る血潮に 小心者は無頼の者と化し
死を怖れる者は ひとりもない
忌まわしい喜びに 酔いしれて
地獄に解き放たれた 悪魔のごとく どよめき笑う
そして 東の空に 紅い月が昇る時
私は ひとりの若者を殺した!細く美しい 弟のような青年を
無残にも殺(あや)め 喜びに浸る
血塗(ちまみ)れた髪を前にして 私の心は満たされる
血の気の失せた 美しい青年よ!
私は鉄剣を揚げ 歓喜の雄叫びをあげ
青年は 虫けらのように 身もだえる
熱気を帯びた戦場を 埋め尽くす屍(かばね)
我々は 勝利をものにした!Ⅱ
かつては若かった我々も 今やすっかり年老いた
もはや 空の美しさに心を酔わすことはない
地獄をつぶさに見つめ
我々の目は 焼けただれた
生きて還る者よりも 戦い命果てた者は幸いだ
死が 記憶を洗い清め
すべてを忘れ去ることができるから
しかし 生きながらえた我々に
忘却などあり得ようか我々は 心に刻みつける
未来永劫 春は忌ま忌ましく 夜明けは恥辱にまみれ
安らかな眠りは 二度と再び訪れはしない
あの戦場の火が消えた日から
騒ぐ風は鳴り止まず……
かつて 朝の風は喜びにあふれていた……
至るところに もがき苦しむ青年の姿が見える
私は うら若き青年を殺した!
送り届けられたこの詩を、母のアンはウォルターの兄のジェムにだけ見せたとあります。そして、ウォルターは誰かを突き殺してはいないが、見てしまったんだ、彼より図太い自分でさえ、と言いかけて言葉を濁すジェムは、自分の二人の息子たちのことをも考えずにはいられません。
そしてアン自身は「落ち着き払って」こう言うのです。
「今にしてみれば、ウォルターが生きて還ってこなかったのは、幸いだったと思うのよ。あの子は戦争の記憶をもっては生きていかれなかったでしょうよ……無駄に犠牲になった多くの尊い命を目にしたのなら、そのおぞましい恐怖の記憶が脳裏に焼きついて離れなかった……。」
「アンの娘リラ」の中で、アンがどれだけウォルターを愛し、その死を悲しんだかを私は知っています。その彼女が「生きて還ってこなかったのはよかった」と「落ち着き払って」言い切る。アンでなければ言えず、モンゴメリでなければ言わせられないことばです。ウォルターを誰よりもよく知り、愛している母だからこそ言えることばです。深く激しい愛とともに、厳しい冷たさや強さも常に秘めていたモンゴメリにしか書けないことばです。
「アンの娘リラ」を読み返すたび、私はウォルターを失い、アンと別れを告げたと思って来ました。私の思いや知識を彼らに伝えることは、永遠にかなわないと実感してきました。しかし、そうではありませんでした。ウォルターは戦場で、パウルと同じように殺した敵を「弟のような」人間として見ていました。彼は勇敢な兵士として祖国のために死んだのではなく、人を殺すことを苦しみつづけていました。それを理解した母のアンが「死んでよかった、生きて帰らなくてよかった」と冷静に断言するほど、彼のその悲しみは深かったのです。
そして作者のモンゴメリは、第二次大戦のただ中にあって、死の間際まで戦争を嫌悪する小説を書き、それを世に出そうと努力していたのです。
村岡恵理「アンのゆりかご ―村岡花子の生涯」(新潮文庫)を読むと、村岡花子もまた、戦争中に必死になって「赤毛のアン」の原稿を守り、さまざまな障害をのりこえて翻訳を続けたことがわかります。その彼女が見ないまま死んだ「アンの想い出の日々」の原稿も長いこと放置されていたのが発見され、孫娘の手で翻訳され、今こうやって私のもとまで届いてきました。
おかげで私は、ウォルターもアンも、私と同じ思いで生きるようになっていたことを知りました。他愛もないことかもしれませんが、これは私にとってやはり大きな幸福です。「生きていてよかった」とさえ、心から口にしないではいられません。
これからも私は戦争に反対し、平和を守ろうとするでしょう。その他にも、世の中や未来のためによいと思った、さまざまなことをするでしょう。そのために大きな敵や強い敵と対決するのはまだしも、親しい人たちや愛する人たちと対立し孤立することもきっとあるでしょう。
昔、「アンの娘リラ」を読んだとき、私はそれを覚悟しました。それは今も変わりません。しかし、今の私にはそれだけではなく、もう一つの予感があります。どれだけ対立し、理解しあえないように見えたとしても、私の好きな人や大切な人とは、きっとまた、必ずどこかでいっしょになれる、必ずまたいつか会えるだろうという予感です。
何十年もの時を経て、いくつもの偶然や幸運が重なって、ウォルターやアンをとりもどした、ささやかな体験が私にそれを信じさせるのです。
5 そしてまた、新たな課題
けれど、新たに知った事実は、私に予想もしなかった幸福とともに、更にまた重い問題もつきつけて来ました。
文学史を教えているとき、学生たちにもよく言うのですが、私たちは歴史を読むとき、その後に起こったことの数々をよく知っている、今のこの現在から、その当時をふり返って眺めます。しかし、その時点、その瞬間に生きた人々にとって未来はまだ何も決定されていない闇です。
チャップリンの映画「独裁者」が高く評価されるのは、ヒットラーを完全におちょくって愚かな悪役として描いたあの映画(恐ろしい怪物ではなく、滑稽で孤独な存在としたところにチャップリンの卓抜な才能と正確な視点がわかります)が作られ公開された時点では、まだアメリカは参戦しておらず、ヒットラーに対しても現在のように世界は完全に否定してはいなかったということです。ある意味微妙な時期でした。だからこそ、チャップリンの勇気と慧眼が称賛されるのです。
「アンの想い出の日々」の原稿が出版社に持ち込まれ、それが公開も出版もされなかったことを、当時の状況から考えて当然と思うこともできますが、もしかしたらその時点では、ヒットラーもナチスドイツも、まだ完全な悪として世界が断罪していたわけではなく、連合国側でもアメリカでもカナダでも、たとえば今の北朝鮮やシリアに対するように、外交や経済封鎖など戦争以外の手段で対応することも可能だったのかもしれないと思うと、戦争への嫌悪と否定を色濃く盛り込んだ「アンの想い出の日々」が出版され、人々に戦争反対を訴えて情勢を動かす可能性も、そんなに途方もなくあり得ないことではなかったのかもしれません。少なくとも、「チボー家の人々」でジャックが戦線の上から兵士たちにまくビラよりは現実的で効果的だったのではないでしょうか。
戻せない時を戻し、その時点に返ってモンゴメリの原稿を手にした編集者や出版社と同じ立場で考えるとき、生まれてからこれまでに、一度も考えたこともなかった疑問が私の心にきざします。
第二次世界大戦は回避できたのか? ヒットラーのナチスドイツ、ファシズムのイタリア、天皇制の日本と戦わない選択肢は存在したのか?
戦わざるを得なかったのか、戦ったことは正しかったのか。そして、その結果、ドイツ、イタリア、日本が敗北したのは、悪の敗北だったのか。それは正義の勝利だったのか。戦争をしたこと自体がまちがいの、勝者のいない戦争だったのか。
歴史はさまざまにねじれながら、私たちの前に姿を現します。
徳永直の「妻よ眠れ」という小説は、この作家の代表作「太陽のない町」以上に私が好きな、戦争中に病死した無学で素朴な妻を描く作品ですが、最後に近く村に来た進駐軍の兵士を、自由な国から来た明るい存在としてながめています。それが作者の本心だったでしょうし、私は好きな場面ですが、共産党員でもある作者として、この描き方はプロレタリア文学の観点からは「アメリカ軍は解放軍ではない」と批判されることもあります。
二〇二三年の現在、プーチンのウクライナ侵攻、それに対抗するアメリカやヨーロッパ各国のウクライナ支援を基軸として、世界はまさに答えの出せないさまざまな問題を私たちの一人ひとりにつきつけつつあります。正義が勝利するという明快な図式は、そう簡単に浮かび上がりません。
おそらく、最も単純に正確に選び取れる方法は、ひたすらに平和を希求し、その可能性を探り続けることでしかないのではないかと私は今、考えています。平和が生む、秩序の維持に名を借りた圧政や人権侵害を防ぎつつ、それでも、そこから始め、そこに行き着かなければならない。どんな時点でも、どんな地点でも、そこからしか、見すえられる風景はないし、歩みだす方向もないのです。知恵と力と優しさの全力をふりしぼって、そのために、私たちは生きなければならない。
この原稿を書き始めてから十年近い年月が流れ、個人的にも世界でも、多くの変化がありました。
今、二〇二三年の八月に、私が到達している決意は、このようなものだということを報告して、ひとまず、この文章を締めくくっておきます。