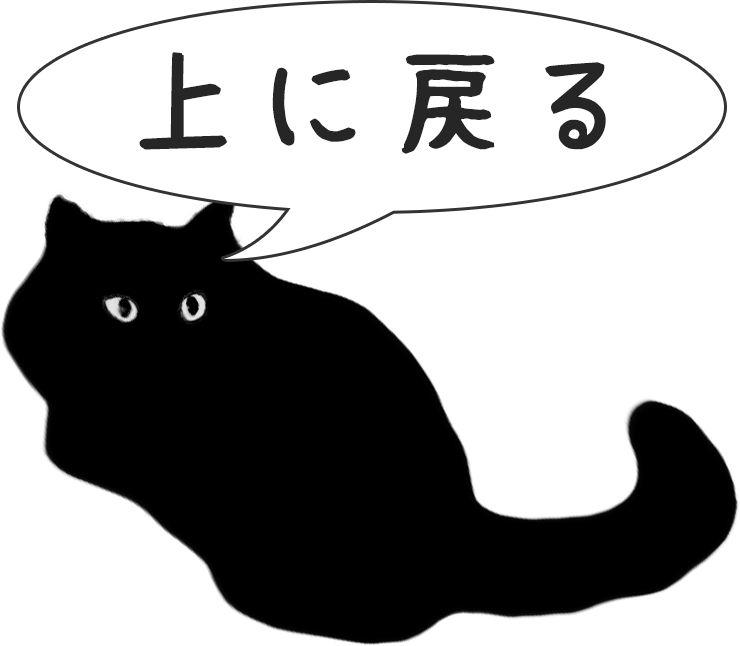あ~れ~
今日届くはずだった本は届かず、次回の授業で使おうと思っていた黄表紙は見つからず、朝、固い肉をかじっていたら、奥歯が一本ぽろっと欠けるか抜けるかしてとれてしまうし、何だかもうしまらない一日。まあ、俳書の読書会はいつもの通り面白かった。
一田子は谷のながめや初ざくら
(「め」がなかなか読めなくて、「り」か「れ」かと言い合ったあげく、「め」と気づいたら谷を俯瞰してる光景じゃないか、と一気にまとまった。)
夜ざくらや腰にふわふわ市女笠
(これ詠んだの、絶対おじさんですよね、と誰かが言う。)
紅梅や尼が絵ときの袈裟御前
(安珍清姫や袈裟御前の絵解きは、どーせ女はつつましく、って教訓になるだろうからいや、とか、今でもそういう語りをしてるんだろうか、と話し合う。)
梅が香や吹矢ながるゝ藪の水
(これも多分、境内のはしかどっかの小川に、屋台かどっかから流れてきた吹き矢が浮かんでるんだろ、ということにした。)
などなど、わかるようなわからないような句が、そこそこ面白い。
授業の黄表紙なんだけど、「無益委記」の入っている全集本が見つからず、「御存商売物」のコピーはあるので、これにしとこうかと思うけど、「御存商売物」って、いわゆる擬人化の「異類物」としちゃ名作なんだけど、いろんな書物が出まくって、受講生、わかるかな、拒否反応起こさないかな。詳しいことは放っといて、青本、赤本、黒本と、八文字屋本あたりのイメージを知ってくれればいいぐらいにしとくかな。私は昔読んだときは、最後に調停役で登場する源氏物語と唐詩選の本が(人間の姿で)「かわずが鳴きますねえ」などと優雅に話しながらあぜ道を歩いて来るのが、妙にそれらしくて好きだったんだよな。
「無益委記」は、この前買った「江戸の黄表紙」にも入ってるから、明日それをコピーしに行ってもいいけど、でも明日は上の家の片づけに、今度こそかかりたいんだよなあ。五月中には何とか、めどのめの字でもつけておかなければ。
朝ドラ「あんぱん」は、ヒロインが軍国少女になってる設定が、とても新鮮でいい。私の母だって、戦後は共産党と社会党以外は投票したことなく、戦争反対の署名やデモに走り回っていたけれど、「戦時中は本当に軍国少女で、米兵がパラシュートで降りて来たら、竹槍で殺そうと本気で思っていた」と、いつも言っていた。母は長崎の活水短大を出ていて、在学中は国文学以外はみな英語の授業で、教師も校長も皆外国人の宣教師で、キリスト教にもなじんでいた。その人にしてそれだった。田辺聖子氏も同じように軍国少女だったことをエッセイその他で書いている。
私だって、学生運動してる時は、革命のためや弾圧に抵抗するためには、死んでも殺してもいいぐらいの気分でいた。帝政ロシアのナロードニキの学生たちだって爆弾投げてひどい支配者を殺したし、その彼らをたたえて、石川啄木は「ココアのひとさじ」なんて詩を書いた。まじめで元気な若者は、健全なまま、テロリストにも特攻隊にもなる。それを狂気だとか洗脳されてるとかいう現代の私たちもまた、ひとつの時代と社会とに染められ影響されている。中立でも無色透明でもない。それはいつだって意識しておくしかない。