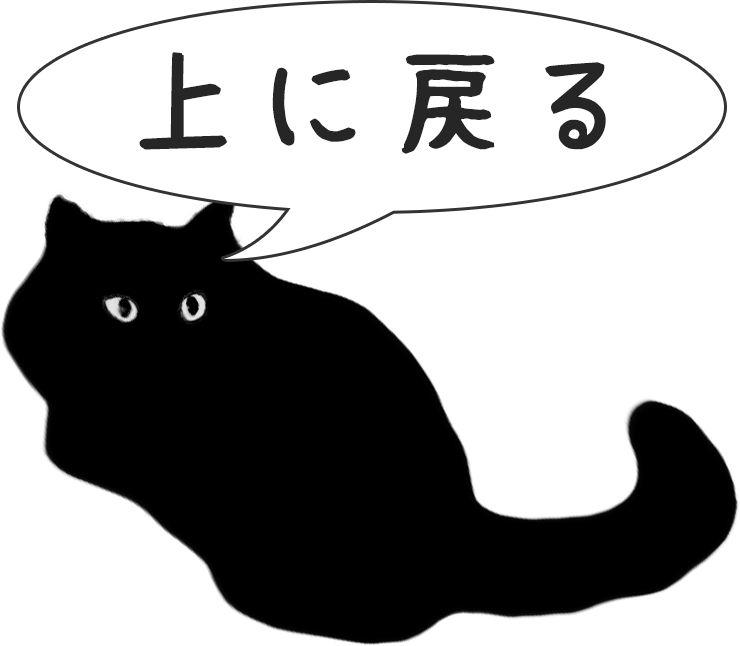青本
大河ドラマ「べらぼう」が、わりと人気のようでちょっとうれしい。蔦重関係の本もけっこう出版され始めたが、授業のテキストにするにはまだちょっと高すぎるし、あまり多すぎて中身がチェックできないので、買うのにためらう。玉石混交で大人買いしてしまうのも、江戸文学で飯食って来た人間の心意気かもしれんけど、どうしよっかなあ。
それにしても、変体仮名(草仮名)を普及させるには、いいチャンスかもしれないんだがなあ。黄表紙なんて、読む練習用にはもってこいなんだけど。
昨日の放送では、こちとらいつもおなじみの、「金々先生栄花夢」がやたら詳しく紹介されて、何だかちょっと、くすぐったかった。
ただし、あんな緑色の表紙の本は今では全然残っていない。皆、色褪せた黄色のばっかり。「青本」と当時呼ばれていた本が、何色だったかというのは、論文もいろいろあるんだけど、結局結論は出ていない。それを、緑色の表紙があせて黄色になったんだという解釈をとって、あんなきれいな緑色の本を目の当たりに見せてくれるのは、何だか妙にどきどきわくわくする。
吉原というか遊郭というか売春というかを舞台にすえて描く構想は、まだときどき批判的な意見も見る。根本的な姿勢や視点が考え抜かれてしっかりしているドラマだから、私は安心し肯定しているが、そういう批判や心配は、ものすごくよくわかる。江戸文学の研究者に女性がまったくと言っていいほどいなかったのも、それと関わるし、私自身も自分の研究でも教師としての授業でも、それをどう整理するかは、激しく迷ったし、苦しんだ。その時の体験や心情を書いた「楽しいお仕事」というエッセイをここで紹介しようと思ったが、『江戸の女、いまの女』という、もう今は絶版になった本の中に収めてしまって、ここでリンクができないので、くやしい。まあぼちぼちと書いていくかな。
さしあたり、大河ドラマで私が感心しているのは毎回の映像だ。吉原の華やかさと貧乏たらしさ、美しさといかがわしさを、色彩や光線で、みごとに表現していると思う。悪や異常のまがまがしくおどろおどろしい地獄図会的魅力でさえなく、どこか、まともで健康でけなげでつつましく、けちくさい。どうやったら、あんな雰囲気を出せるのかと、つくづく感心してしまう。
写真は愛猫の故キャラメルをしのんで買ったストックの花。彼の命日ももう近いんだよなあ。