「水の王子」通信(144)
「水の王子 山が」第三十七回
【兄は驚かない】
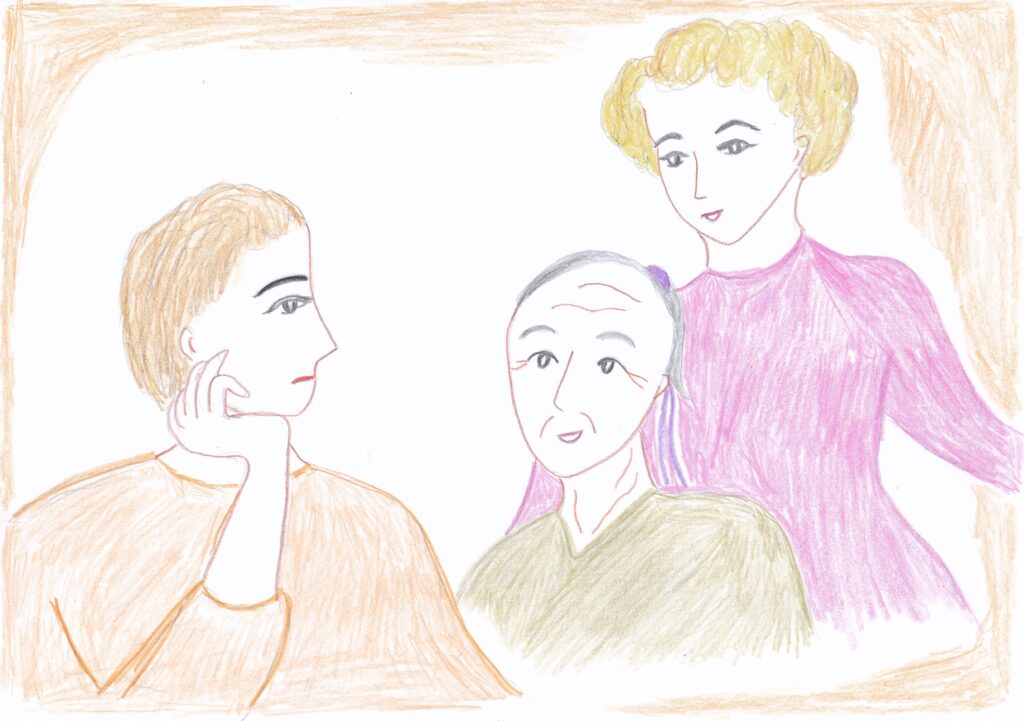
「ああ」コトシロヌシはうなずいた。「それであんなに気にしてたのか、タカヒコネは彼のこと。だけどいったい誰が化けてるんだろうな。昔、彼に会ったことのある村人もちっとも疑ってなかったし、何よりあのすごい力はただ者じゃない。弟子にしたって相当の何者かなんだろうが」
「シタテルヒメだよ」タカヒコネがため息をついた。「君の妹」
「何?」さすがにコトシロヌシが目を見張り、口を開けた。
「それって、村を出て行った人か?」ニニギも固まっている。「だってたしか、ものすごい美少女だろ? サクヤなんか目じゃないって、古い村人は皆言ってたという」
「それは大げさ」コトシロヌシが訂正した。「サクヤの方がきれいだよ。見る人の好みにもよるだろうけど、彼女の方がずっと美人だ」
「そうか?」ニニギがうれしそうにした。「サクヤが聞いたら喜ぶな。絶対かなわない、比べものにならないって、耳にたこができるほど聞かされたって言ってたし」
「サクヤはちょっと不安定で危なっかしい感じがするけど、シタテルヒメはそうじゃなかった。いつでもしっかり足が地についてて、自信にあふれて明るかった。そこが多分、皆の好みがわかれるところなんだろうが」コトシロヌシは首をふって酒をすすった。「そうか、彼女か。スクナビコの弟子になってたんだな」
「驚かないのか」タカヒコネは気味悪そうにコトシロヌシを見つめた。
「なぜだろうな。あんまりふしぎじゃない」
「本気かよ?」
「言われてみれば、いっしょにいたり、君の話を聞いたりしていて、何となくスクナビコって妹っぽいと感じたことがあったんだ」
「どこをどうやったら、サクヤもかなわない美少女と、あのはげ頭の食えないじいさんが似ているなんて思えるんだよ?」
「うーん、そう言われてもな。ただ何となく」コトシロヌシは細いあごに長い指をあてて考えこんだ。「余裕というのか安定感というのか。彼女絶対まちがったことなかったしなあ。すきや見落としもないし、そのくせちょっと意地悪で、いたずら好きで。君の治療でわざといじめてるって言うのも、いかにもだよ、そう考えたら」
「それはひどいな」ニニギがあきれる。
「でも、がまんできないほどじゃなかったんだろ?」コトシロヌシがタカヒコネに言った。「私や兄をからかう時もそうだった。かげんを知ってて、とことんひどいことはしない。基本的にはやさしいんだよ。タケミナカタなんか、いじめられてることにさえちっとも気がついてなかったし―どうした?」
※
「ああ、そっちの話もあったんだ」タカヒコネは額に手をあてた。「おれは草原で、いや都でもいろいろあって、たくさんの人を殺して」
「そうらしいな」
「すまない、もっと早くに言うつもりだったんだが、君の兄さんも、タケミナカタもその中の一人だった」
二人はちょっと黙っていたが、やがてニニギが「それはしかたがないだろう」と言った。「私だって戦いのなかで、ヨモツクニ以外の関係ない人々をどれだけ殺したかわからない」
「戦いの中じゃないんだ」タカヒコネは首をふった。「都の王だったとき、都の中に新しい考え方の集団があって、ヨモツクニとは関係なかったし、私たちはいろいろ迷ったんだが、結局危険過ぎるからと、闇に葬ってその組織をつぶすことにして、スサノオがおれにそれを実行するよう命令して、おれはまず彼を殺し、その後、組織を壊滅させた」
「君は王だったのに、自ら手を下して?」
「絶対に秘密は守らなくてはならなかったし、そんな汚いことを頼める者は都の中にはいなかった。まっすぐな心の人たちばかりで」
「わかるような、わからんような」コトシロヌシはつぶやいた。「だが、噂に聞いてもそういうところなんだろうな、あそこは。それで、兄がその集団にいたのか」
「中心にいた。私とも親しかった。友人で、いろんな未来について話して、毎日すごしていた」
「だから最初に殺したのか」コトシロヌシは静かに言った。「それもまた、わからんじゃないが…父と母は知ってるのか?」
「オオクニヌシには話した。山の崩れたとき、がれきの下で。だが彼はもう知っていた。ヌナカワヒメからもらった薬を、こっそりタケミナカタに飲ませていたんだ、村を出る時に。それは殺した者の身体をむしばんで、傷が治らなくして死に至る薬だった。オオクニヌシは私を見ていて、それに気づいて…とても苦しんでいたようで」
「何てことだ」コトシロヌシはつぶやいた。
「スセリには話せなかった。オオクニヌシ以外の誰にも言ってない。あんな、生き埋めにされるようなことがなかったら、おたがい口にしなかったさ。それでも、スセリには話さなくちゃと思っていた。オオクニヌシもそう望んでるのがわかってたし。でも、なかなか言えなくて、つい先延ばしにしてしまってた」
「もしかして、それを今日話したのか」ニニギが言った。「それで大騒動になって、だから逃げ出してきたのか、君は」
だがコトシロヌシはけげんそうだった。「何となく」と彼は言った。「母がそう騒ぐとは私には思えないんだが」
