『大才子・小津久足』感想(7)
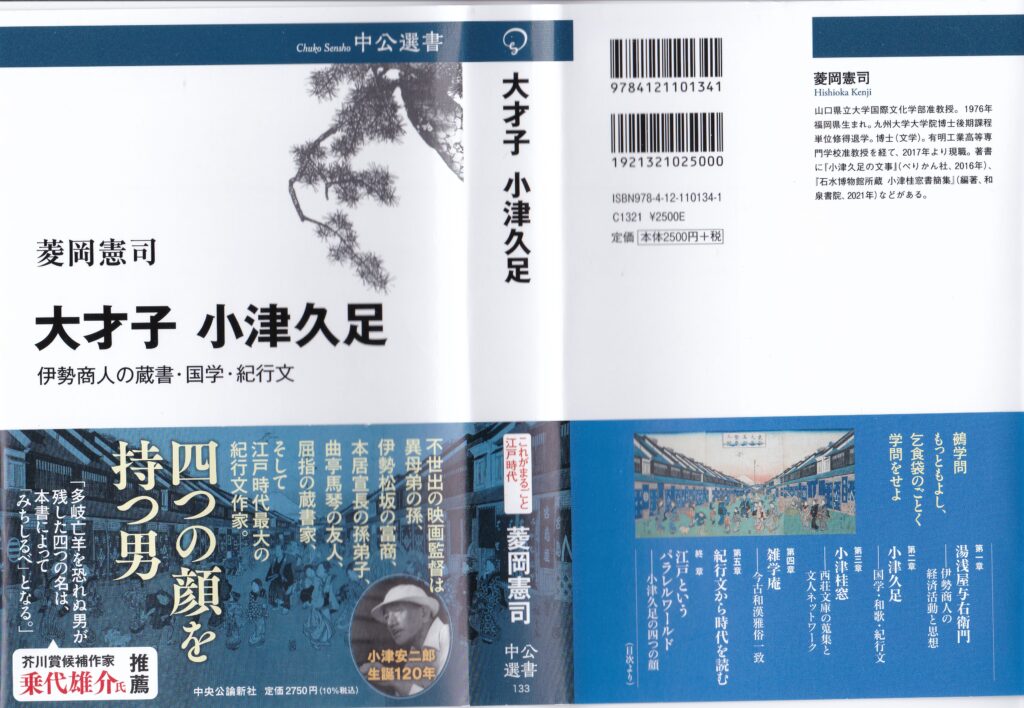
創作の動機
前二回で私がくり返した、「数万首の歌を詠んでいるような歌人たちのそれぞれの特徴を説明するのに、その中の数首の歌を紹介することで、いったい何かがわかるのか、伝わるのか」といった思いは、たとえば、そもそもその歌人は何が楽しくて、何を求めて和歌を詠んでいるのか、また、できれば『文化史のなかの光格天皇』に収録された大谷俊太氏の「光格天皇と趣向」にある、光格天皇は歌において「趣向」を好む、といったような指摘がどの歌人についてもわからないものだろうか、といったようなことにつながっている。
私は和歌史の本なんか、ほんとにろくすっぽ読んでないので、同様の指摘は他にもあるのかもしれないが、たとえば、「この歌人は風景描写が好き」とか「日常の生活を詠むのが抜群にうまい」とかいうことが各歌人についてわかったら、さぞかし覚えやすいだろうということを思う。
しかし、これはもう明らかにないものねだりであって、そんなことが各歌人について把握できるほど世の中は甘くない。小沢蘆庵や香川景樹や賀茂真淵の歌集を通読しても、そんな印象はつかめない。けっこう似た歌が多いし、その人個別の特徴が浮かび上がる歌なんて、そうそうはないのである。というのが、しろうと同様の私の印象だ。
貝原益軒の場合
我田引水で恐縮だが、私は自分の紀行研究のスタートになった貝原益軒について調べたとき、彼のエッセイ、手紙、教訓書その他の中から、彼がさまざまな執筆をするエネルギーとなり支えにしているのは、「自分はこんな平和な世の中に生まれて幸福に暮らしている。そのことについて少しでも感謝したいし、天や世の中にお礼をしたいが、何しろ何の才能もないから立派な学問を築くようなことは何もできない。そういう立派な研究は多くの人がすでにしている。だから、せめて、これまで誰も相手にしなかったような広い庶民にもわかるようなことばでいろんな知識を世の中に広めることで自分の役割を果たしたい」という理屈なのだと理解できた。
全国基準で押しも押されぬトップクラスの大学者の益軒がこういうことを書くのははっきり言っていやみでしかないが(笑)、これが益軒の学問から職場での勤務から家庭での日常生活から、すべてに通ずるパフォーマンスでプレゼンで、そしてけっこう本気でもある。もちろん、これだけではないが、大好きな文章を書いたり読んだりすることに没頭する言い訳として、彼の根底にはいつもこの理屈がある。
またはしたない自慢話をしてしまうと、私はこのことを書いた「貝原益軒と紀行文」という論文は、ちょっと型破りの手抜きのような気がして、自信がなかったので、抜き刷りを全然人に送ってなかった。その後、これを引用して九州大学の国文学会で発表したら、中野三敏先生が質問をされて「この論文は僕はもらっているかな」と言われたので、「いえ、さしあげていません」と言うと(あとで、そのことでさんざん皆にあきれられたし笑われた)、先生は「僕らもこういう風に、作者の思想と創作を結びつけたいんだけど、なかなかできない。とても興味深い」とおっしゃって下さって感心して下さったようだった。
ほめていただいたから自信がわいたわけでもないが、このようなかたちで、作者の思想と日常と創作動機を有機的な全体像としてとらえることができた自分は幸運だったと思う。そしてそれ以降も今も、あらゆる作者と作品を、このようなかたちでとらえなければ何だか完全燃焼できない欲求不満が残るようになったのは、ビギナーズラックで万馬券を当てたようなささやかな不運なのかもしれない(笑)。
それにしても私のこの論文の分析は理路整然とはしているが、雑でもある。学生によく、「資料を多く集め深く考えると、矛盾も多く生まれて、論は支離滅裂になって爆発しやすい。わずかな資料しか見ないで強引に構成すれば、すっきりして説得力ある論文になる。後者の方が評価は高くなるかも知れないが、私は個人的には前者の方が好き」と言ったりするゆえんだ。菱岡君はこの本で、私よりもはるかに詳しく資料を集めて、綿密な分析を行って論を構築して行っている。もちろん支離滅裂になっていないし、爆発もしていない。
創作を支える情熱
和歌を詠む歌人たちの中に、私が雑なりに益軒でとらえたような、そういう理屈や支えや開き直りはないものか。もちろん時代によってもちがうし、個人の環境によってもちがうが、ゆるぎないそういうものがなければ、そんなに大量の創作はできないはずである。
おそらく、その始まりには、和歌だって恋愛関係のアイテムや宴席での遊びや人間関係や出世の手段として実用的に使われていたのかもしれない。平安朝文学の研究者で和歌や物語や漢籍や要するに全般に詳しい工藤重矩氏に私は一度、「要するにあなたの主張って、平安朝は意外と散文的、ってことよね」とむちゃくちゃな著書の感想を述べ、彼はまんざらでもないようにむふふと笑っていた気がする。
それがやがて勅撰集から歌の家としての権威も生じ、貴族たちはこぞって甲子園か花園ラグビー場のように、芸術としてすぐれた歌を詠もうとするようになった。それが彼らの創作への情熱を支えたことは否定できないだろう。しかし、そういう「プロジェクト・ランウェイ」風の図式がかなり薄れたにちがいない江戸時代には、歌人たちは何を支えに数万首にもおよぶ歌を毎日詠みつづけたのだろうか。
俳諧の場合には、それこそ皆で連句を作る「座の文学」の楽しさが、いわば接待ゴルフにも等しい娯楽として作者たちを夢中にさせたことが何となくわかる。和歌の世界でも、先の森為泰の日記や、「寄生木草紙」に登場する、下手っぴいな歌を詠みまくる若者の姿から、似たような交流の楽しさ、優雅な趣味世界への憧れなどはうかがえる。
もっと著名で有名な歌人の場合は、それぞれどうだったのだろう? ライバルを蹴落とす喜び? ことばをあやつる魅力? 自分の心情を吐露できる快感? 最新号のカタログハウス「通販生活」2023春号の巻頭対談で現代歌人の俵万智は、「歌を詠むのは、日記というより手紙に近い」と話しているが。
菱岡氏も指摘するように、特に国学者の場合には、紀行も和歌も、伝統的な和文の文章を磨くためのトレーニングとして意識されていた。彼らはバレリーナやピアニストやアスリートが毎日のエクササイズをこなすように、とにかく歌を詠み、紀行を綴っていたはずだ。だが、久足の場合などは、いろいろあって宣長を批判し、国学から離れた後には、そのモチベーションを惰性で維持していたわけではないだろう。何が彼を支え、かりたてたのか。
私のこういう疑問は、あるいは和歌の研究者の中ではとっくに共有されている、暗黙の了解事項なのかもしれない。それはこれから私も勉強するとして、当面は菱岡氏がこの本の中で、小津久足の場合はどうだったかについて、ふれている事実のいろいろを追っかけてみたい。あー、すみません、また中途半端になりました。今度こそ、次は紀行について話します。
