「水の王子・丘なのに」(14)/219
「水の王子・丘なのに」(第十四回)
【クラドの告白】
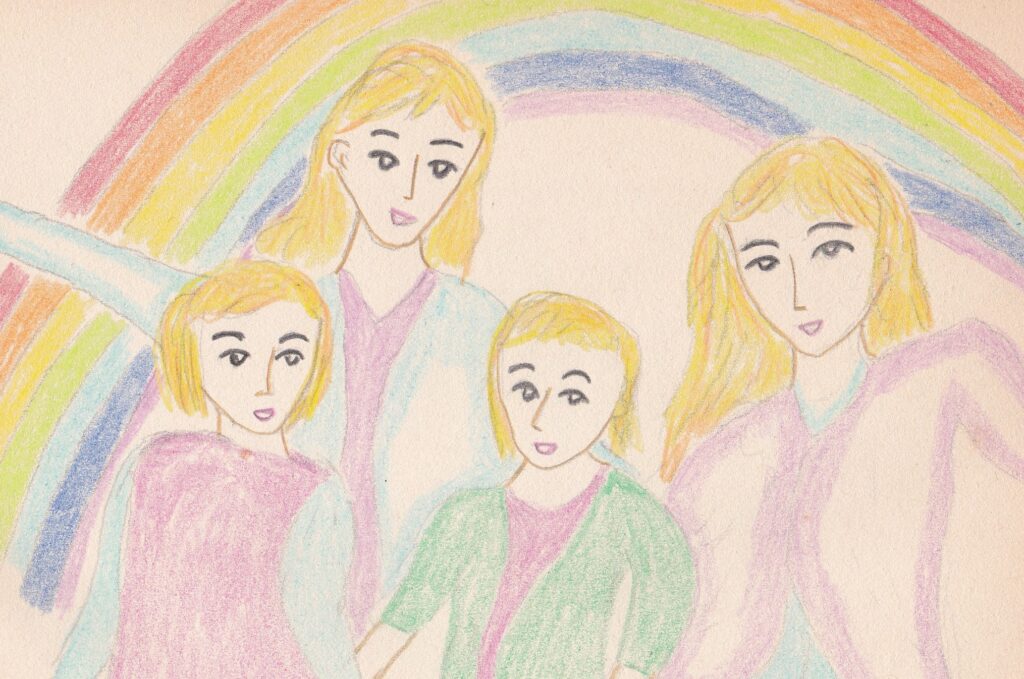
タカヒコはクラドの肩に手をおいた。
「いったい、何があったんだ?」
クラドはぼんやり顔を上げ、前の茂みの花を見つめた。
「タクハタ姫が病気になった」彼は何の感情もまじえずに言った。「だんだん悪くなって、それで妃はタヂカラオの町に連れて行った。そこでずいぶん回復してね、弓の競技に出て大人たちに勝利するまでに元気になっていたんだが、やがてまた悪くなって今度はそのまま、もうだめだった。あそこの町がとても好きだったから、そこで葬って妃は一人で戻って来た。妹のミズハ姫はその間ずっと、私とカナヤマヒメがこの町で育てていたんだよ。まだ小さかったしね」
何も言えずにタカヒコは、ただクラドの背中をなでた。
「妃は疲れはてていた」クラドは言った。「あの、いつも幸せにみちて笑いをたやさなかった人が、別人のようにやつれていた。私たちも悲しみにみちて彼女を迎えた。ミズハ姫だけがずっと会えなかった母が戻ってきたから、無邪気に喜びをあらわにして、それは私たちにも救いだった」
クラドの指が目の前の土の山をなで、首飾りにふれた。
「悲しみの中に時は流れた」彼は言った。「私たちはタクハタを失ったことからなかなか立ち直れなかった。彼女は私たち一家の、この町全体の希望だった。明るくて、ひかえめで、強くて、皆を楽しくさせた。賢くて、優しくて、そしていたずら好きでもあった。ひとつひとつの何でもないことが、彼女がふれると皆、宝玉のように輝いた。お父さま、と一度私に言ったっけ。あの階段の手すりを私とすべりっこして勝ったら、虹で首飾りを作ってあげる。彼女は虹をあやつれた。虹に好かれていたんだよ。指先も器用で、虹のような色の織物をよく作っては皆にくれた。時々は旅人の手に遠くから、小さい虹をまきつかせては、あわてるのを見て、きゃっきゃっ喜んで笑ってたっけ」
「虹も今、淋しがっているんだろうな」タカヒコはつぶやいた。
「それでも虹は消えなかったし、私たちは生き続けた」クラドは言った。「ただ、妃だけがだめだったんだ。人が変わってしまったようで、二度と元には戻らなかった」
※
建物から出て来た数人の家来が心配そうにこちらを見ている。クラドはそれに気がついて、かすかに笑って心配ないというように手をふって皆を中に下がらせた。
「ある日私は、妃がミズハ姫をおさえつけて、顔をたたいてゆさぶっているのを見た」ささやくようにクラドは言った。「そんな乱暴なこと、動物にも花にも、決してする人ではなかったのに。恐ろしくて、悲しくて、私は必死で二人をひきはなし、わけを聞いたが妃は答えようとしなかった。その目にミズハへの憎しみがあふれていたのが、更に私を混乱させ、苦しませた。ミズハはもちろん、おびえきって、ふるえ上がっていて、口もきけないし、わけもわからないようだった。私は二人を別々にし、当分会わせないようにした。そしてとにかく、二人に優しくし続けた。心をこめて、語り続けた。それで何とか元に戻ったようだったから、また二人を少しずつ会わせるようにして、一応ぶじにすんだけれど、妃はおだやかな中にもどこかミズハに冷たいし、ミズハもどこかしらおびえていた。信じられなかったよ。あんなに幸せで、心からたがいを好いていた家族の姿が、もうどこにもなく、影のように幻のように消えてしまうなんて」
「君は大丈夫だったのか?」タカヒコは聞かずにはいられなかった。「そんな日々がずっと続いて」
「大丈夫じゃなかった。生まれてこのかた味わったことのない苦しみを日夜味わい続けて、私は疲れ果て、なかば狂う寸前だった。何よりも苦しかったのは、妃がそうなってしまった心の動きが理解できなかったことだ。たしかに気まぐれで、とらえどころのないところもある人だったが、でも私には彼女の心のすみずみがいつもよくわかっていたんだ。いらだちも不機嫌も皆、原因の見当がついて、そこをくすぐったり、つっついたりしたら、彼女はきっと笑いだして、また晴れやかな笑顔や清らかな口づけでこたえてくれて、私たちの心は前以上に結びついて、からまりあって、ひとつになった。そうするすべが、手がかりが、もうひとつも見つからない。遠い向こうの崖の上にいる人のように、彼女の心に届くものが何もない。私のそんな様子を心配した家来たちの数人が、私の知らなかったことを話してくれた。カナヤマヒメが…」
クラドの肩をさすっていたタカヒコの手が思わずとまった。「彼女が?」
※
「タヂカラオの町から帰ってきて、私たちが彼女を出迎えたとき、カナヤマヒメが妃に言ったことばだ。私はそれを聞いてなかった。聞いても気づかなかったかもしれない。それほどふつうの、何でもない、あたりまえのことばなんだよ。妃だってふだんだったらきっと気にしなかったんだろう。けれどあのとき妃は疲れきって、悲しみのどん底にいて、その何でもないことばに魂をつかまれてしまった。そして、二度とそれから逃れられなかった」
「それはどんなことばだったんだい?」
「話したくない。口にしたくもない。たったそれだけか、何でもないじゃないか、と思われるかもしれないと思っただけで気が狂いそうになる」クラドは激しく身ぶるいし、タカヒコの手を払い落とした。「私は即座にカナヤマヒメをとらえて、何の説明もしないまま、地下牢に放りこんだ。彼女は今でもそこにいる。生きてる限りもう二度と、そこから出てきてほしくない」
※
「クラド王!」タカヒコは思わず声をあげた。「それは無茶だ。いくら何でも」
「知ってるさ。わかっているよ」
「君らしくもない。仮にもこんなみごとな町の、まともな王のすることじゃない」
「本当はあの女を殺そうと思った」クラドは血走った目を上げた。「次に舌を切ろうと思った。この手で。本当にそう思ったんだぞ。でも、できなかった。そこまでは、どうしても」
わななきつづける、その金色の髪にタカヒコは再び手をふれた。「そんなことをしないで本当によかった」
「そうかな。どうだろう」クラドは吐き出すように言った。「あの女のことはそれきり考えもしていないが、考えたらきっと、そうしなかったことをくやみそうでならない」
※
「それで妃は元に戻ったのか?」
「いいや」クラドは淋しげに笑った。「カナヤマヒメがどうなったかは知らないままだったと思うが、一応見た目はおだやかに静かに過ごしていた。もうこのままでもいいから、とにかくそばにいてくれさえしたらいいとまで私は思い始めていた。けれども、ある日の朝彼女は、タクハタが死んでからいつも着ていた白い衣を着て、ミズハにも同じ色の衣を着せて、彼女を抱いて白い馬に乗り、一散に草原の方に向かって霧の中を走って行った。ミズハは何もわからないから、久しぶりに母が遊んでくれると思って、喜んで、声をあげて笑っていた。妃も笑っていた。声を限りに、狂ったように。そのまま霧の中に消えて、帰った時は一人だった。ミズハの行方を聞こうとして、泡を吹いて疲れている馬を家来に渡して、彼女をあちこち探したら、この奥庭のこの場所で、タクハタの遺品や髪を埋めた仮墓の上で、短刀で自殺していたんだ。悲しみにみちた笑顔のままで」
※
タカヒコはクラドの肩を抱き寄せた。それ以外どうしていいのかわからなかったのだ。クラドは弱々しくタカヒコを押しのけ、ややあらたまった口調で「許してくれ」とつぶやいた。
「許すって、何を?」
「君はきっと、怒っているだろ」力のぬけた声だった。「私と家来たちが嘘をついて、幸せな町のままのふりをして、君をだまし続けていたことを」
「そもそも、家来や住人たちのどれだけが、本当のことを知ってるんだい?」
「どうだろうかな」クラドはぼんやり笑って目を閉じた。「よく知らないんだよ、私も。妃たちが旅に出て、帰って来ると思いこんでいる者も多いだろうし、何もかも知って、わかって、つきあってくれてる者たちもいる。その中間の者たちもきっと多い。皆、もうどうしていいのかわからないんだ。とにかく嘘でもこうしていれば、幸せなふりを皆でしていれば、いつかはひょっとして、嘘が本当に近くなりそうな気がしているっていうか」
「そんなことで本当に何かがどうにかなるって思っているのか、君たちは?」
「私にはもう、これ以外、どうしていいのかわからないんだ。それに君が来てくれて、皆、ますます、夢が現実になって行くような気がして来ていたんだ。昔と同じように君が私と幸せそうに毎日を過ごしてくれて、私たちの嘘の中で疑いもなく気持ちよく暮らしてくれて、まるで、それがすっかり本物のような気が私たちも感じることができて、だから誰もが本当にこの数日間幸せだったんだよ。君をだましていたというならたしかにそうだが、私たち自身が幸せに酔っていたんだ。君がいてくれたおかげで、消えた夢が目の前にあらわれて、皆でその中にいるようで。それだけは信じてほしい。決して君をだまそうとしていたんじゃない」
「私は怒ってなんかない」タカヒコはクラドの両肩をつかんだ。「でも、このままじゃいけないよ、クラド」
クラドは黙って目をそむけた。眠りから覚めるのを拒む子どものように、その唇がわずかにゆがむ。
「どうしろと?」ようやく低く答えがあった。
「とりあえず、カナヤマヒメが妃に言ったということばを私に教えてくれ。いやなら直接私が聞くから、私を彼女に会わせてくれ」
クラドはちらとタカヒコを見て、投げやりに「いいよ」と言った。「家来たちに案内させる。だが、あの女と何を話したか、いっさい私に聞かせるな。私はもう二度と、彼女のことを考えたくない」
