「水の王子・丘なのに」(4)/203
「水の王子・丘なのに」(第四回)
【冗談にもほどがある命令】
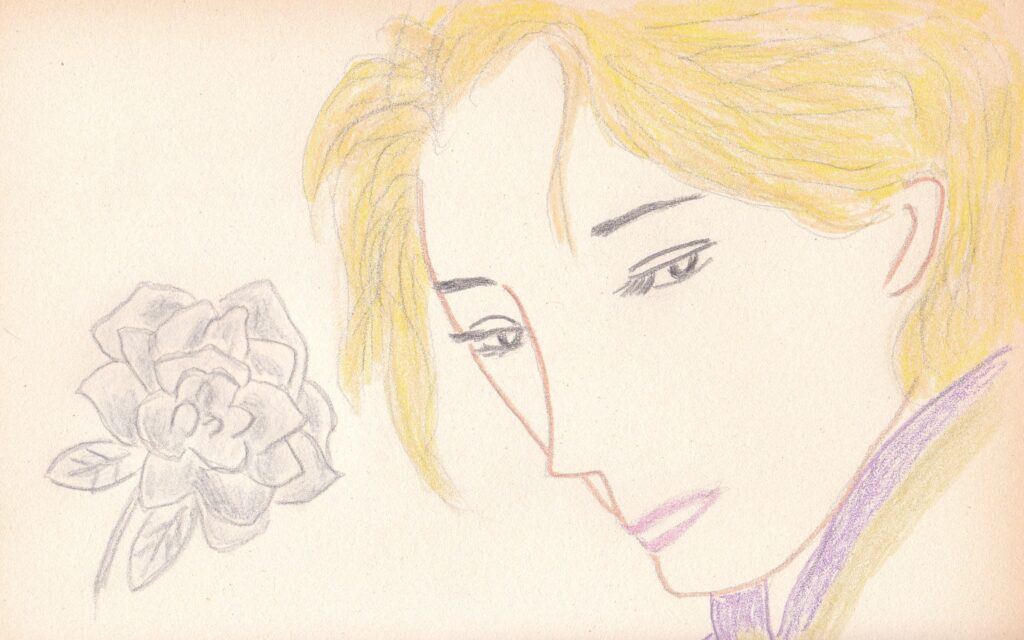
「それでね、君にお願いしたいことというのはですねえ」タカミムスビはあいかわらず、にこやかな笑顔で続けた。「花の町というのを知っていますか? 別名を虹の町とも言いますが。南の方の草原のはずれ、海の近くにある町で、なかなか魅力的なところです」
「名前は聞いたことがあるような気がしますが、あまりよくは…」
「支配しているのは、クラドという若い王です。お妃はええと多分、草原の出身ではなかったかな。カヤヌヒメという女性で、将軍のアワヒメとも知り合いのはずですよ。娘さんが二人いて、夫婦仲もよいし、家来たちともうまくやっていて、たいそう幸せな町とのことです」
「はあ」
「そこの様子が、このところ、少しおかしくてね」タカミムスビは顔を曇らせた。「ナカツクニの村のこともありますし、早い内にどうなっているのか知っておきたいのですよ。クラド王は乱暴なことはしない人と聞いていました。それがこの半年の内に、罪もない立派な学者のカナヤマヒメという女性を、追放したか殺したか、とにかく町から消してしまったようなのです。彼女は人望もありましたし、タカマガハラとの交渉や連絡にもあたってくれていたのです。それがいなくなったのですから、何が起こっているのかまるでわからなくなりました」
あいかわらずタカヒコは、この話の行く先がさっぱりわからなかった。「クラド王は何と申しているのですか」と、とりあえず聞いてみた。
「何も」タカミムスビはまばたきした。
「と、申しますと?」
「君のそういう時の表情は、本当にアメノワカヒコにそっくりですねえ」タカミムスビは、ほれぼれとタカヒコを見、ふり返って黙ったままのタカギノカミとうなずきあった。「まるで彼が、そこに立っているようですよ。これならクラド王も、きっと気がつかないでしょう」
漠然と何だか悪い予感がしたが、それが何なのかタカヒコにはわからなかった。「どういうことか、わたくしには…」
「クラド王はちょっと気まぐれで風変わりなところがあって、人の好き嫌いも激しいのですよ」タカミムスビはタカヒコの問いは無視して続けた。「アメノワカヒコのことはなぜかたいそう気に入っていて、信頼しきっていたようでした。彼が訪ねて行ったなら、きっと何かを話してくれると思うのです」
「ですが彼はもう死んで…」
「その噂は草原には、まだ全然伝わっていません」タカミムスビは「全然」に力をこめた。「君があちこちに姿を現しているから、なおさらのこと」
※
「他にあの町に近づく方法が、今のところはないのだよ」タカヒコが、つばをのみこんで何も言えずにいる前に、沈黙を守っていたタカギノカミが、身体も顔も動かさず、窓の外を見たままで、まるで関係ないことをしゃべっているように、低くよくとおる声で言った。「君は当然、自分が一人で乗りこむ前に、船団を寄せるかどうかしてクラド王と話し合いをしたらどうかと思っているのだろうが」
いやそんなことまだ何も思いついてもいませんが。タカヒコは思った。
「あそこはふしぎな町なのだ」タカギノカミは同じ調子で続けた。「軍隊らしい軍隊もない。だが、霧や靄や霞が常に晴れたりかかったりして、いかにトリフネの操縦が巧みでも、地上からの協力がないと船はまず下ろせない。海からも接近できない。隠れた岩礁だらけでね。さりとて草原からの道は沼と森とが入り乱れて、町の方から見張られていては誰も近づけないし、常によそ者を警告するように虹が幾重にもかかって周囲を取り囲む。このところクラド王はよそ者を町に入れず、近隣の町や村の長たちとの交際も断ってしまった。彼も妃も、ヨモツクニは大変嫌っていた。残酷さや血なまぐささとは、まったく相容れない、繊細な華やかさを保って生きて来た町だ。こちらもそれで安心しすぎていたかもしれない。孤立して自分を閉ざそうと思えば、いくらでも可能な町なのだ」
「ある意味ではナカツクニより、やっかいなのですよ」タカミムスビがのんびり言った。「結局、君にひと肌脱いでもらう他はないというのが、我々の結論なのです」
「ですが、私は生前のワカヒコさまには、会ったこともほとんどないのです」タカヒコはどもった。「いくら外見が似ていると言っても、それだけでは、きっと見抜かれるにちがいありません」
「そこは努力してもらうしかないね。何ごともやってみなければわからないものだ」
「ですがあの、ですがあの」
「君だってタカマガハラの戦士でしょう?」タカミムスビは落ち着いて言った。「もっと自分に自信を持ってもいいのではないでしょうか」
※
「あきれてものが言えないわ!」タカヒメは吐息をついた。「本当に、本当に、それで兄さま、引き受けちゃったの?」
「他にどうしようがあったんだ? 断り方もわからなかった。逃げ方だって」
「生存本能とか防衛本能とか、そういうものはないわけ、いったい兄さまは? 草原のウサギなみにも?」
「もう言うな」タカヒコはしょんぼり答えた。「おまえなら、さぞかし立派に、きっぱり断れたんだろうよ。そもそも私は、あんまり人にものを頼まれたことがないんだもの。なれてないんだ、そういうことに」
「そこは同感」タカヒメはうなずいた。そしてまた何か言いかけたが、思い直したように口を閉じて、そのまま荒っぽい足どりでへやから出て行った。
タカヒコは、まだぼうっとしていた。それから数日、ずっと雲の中を歩いているように何も考えられなかった。
何だかこのごろ、いろんなことが、うまく行き過ぎてると思ってたんだよなあ。
何となく、そうも思った。
ナカツクニの村に自由に出入りして、あそこの人々と親しくもなって。
きっと、ものすごくひどい目にあう前に、誰かがかわいそうに思って、この世で最後の楽しみをどっさり与えてくれたんだ。
そんなことまで考えてしまって、彼はますます落ちこんだ。
