水の王子・「川も」9
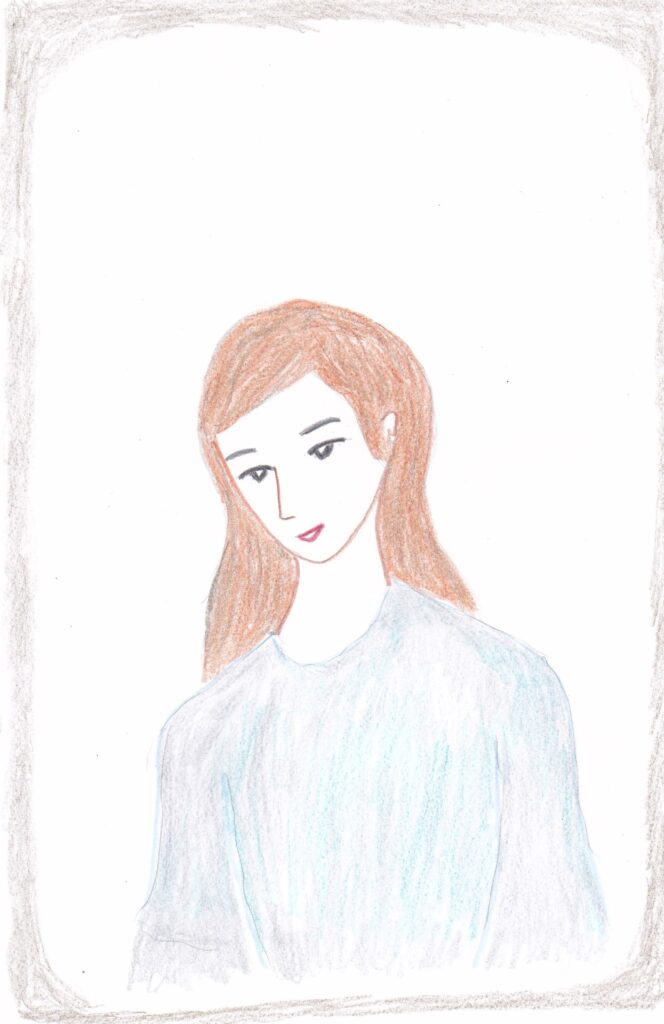
第五章 夜の声
ハヤオの胸のむしゃくしゃは、それから何日たっても一向に治まらなかった。
かりそめにも、どんなかたちででも、好きだと言ってもらったのだから、ちょっとぐらいはうれしくてもいいはずだと思うのに、なぜだかちっとも楽しくなく、思い出せば思い出すほど、いやな思いがするばかりだった。
これまで旅の間でも、ナカツクニの村でも、かわいい女の子や年上のきれいな娘から、好きよとかすてきとか言われたことは何度かある。別にそんなにかわいくもきれいでもない女の子や娘からも何度かある。
でも、どんなときでも程度の差こそあっても、うれしかった。こんないやな気分にはならなかった。「おれもさ」と言って、けっこう仲よく遊んだりもした。
今度はどうしてそうじゃないんだろう?
ハヤオがそっけないからか妹娘はあれきり何も言わなかったし、村の子どもたちと遊んでいても、ヒルコやツマツと仕事をしていても、そのことを話すきっかけはなかったし、話す気にもなれなかった。
ハヤオがいつもよりむっつりきげんが悪いのを、ツマツは気づいてないようだったし、ヒルコも気にとめていないようだった。
それもハヤオをいらつかせていたのかもしれない。ハヤオとは逆にどことなくヒルコは浮かれて、のびのび楽しそうだった。姉娘にも妹娘にもあいそよく、きげんよく相手をしていたが、まさにまったく気をつかわないでいい、どうでもいい相手に接しているようで、ナカツクニの村にいた、犬だかオオカミだかみたいなけもののイナヒとか、極彩色の大きな鳥のウガヤにだって、もっと心をこめた優しさと敬意をこめて接していたんじゃなかったっけと思うぐらいだった。実のところ、もうそんな、どこかはかなく細やかな心のヒルコを、ハヤオは思い出しにくくなっていたのだ。
こいつ、この村が好きなんじゃないか? そう疑ってしまいたくなるほどに、ヒルコはこのごろ何だか荒っぽく、生き生きしていて、冷たかった。よく笑うし、よく食べるし、夜はあっという間にすやすやぐっすり寝てしまう。絶好調だな、といやみの一つも言ってやりたいところだが、今のハヤオには何となくその元気がなかった。
※
ツマツとモモソはたしかに貧しい暮らしだったが、特に不幸そうではなかった。昼間は黙ってそれぞれの仕事にいそしんでいたが、夜になると寝床の中で遅くまで楽しそうにいろいろしゃべって笑っていた。「やかましくって眠れなかったのじゃない?」と、一度気にしてモモソがわびた。「他に楽しみがないものだから、夜も灯をつけておくのがもったいないし、寝床の中でしゃべるぐらいしか時間つぶしができなくて」
「あ、全然心配しないでいいです。ちっとも気にならないから」と即座にヒルコが答え、ハヤオは内心そりゃそうだろうと思った。このごろヒルコは枕に頭を沈めるが早いか、気持ちよさそうに、もうすうすうと寝息をたてはじめてしまっているからだ。ときどき、おぼろな光の中で見ると、楽しい計画でも考え中のように唇を小さくほころばせているのが無気味である。何をたくらんでいやがるんだと思った。
昔は、いやほんのちょっと前までは、ツマツ親子に負けないほど、寝ながらあれこれしゃべっていたのに。そう思うとまた腹が立つが、しかしハヤオは淋しいとは思わなかったし、不安も感じていなかった。こんなに勝手にくつろいでいるのは、ヒルコがハヤオを全然警戒しておらず、気を許して安心しきっているからだということは、わかっていたし、知っていた。ハヤオが心配したり怒ったりしていることは何か別のことで、それが何かは、ハヤオ自身にも、よくわからないのだった。(つづく)
