水の王子・短編集「渚なら」13
第八話・困った人ね(下)
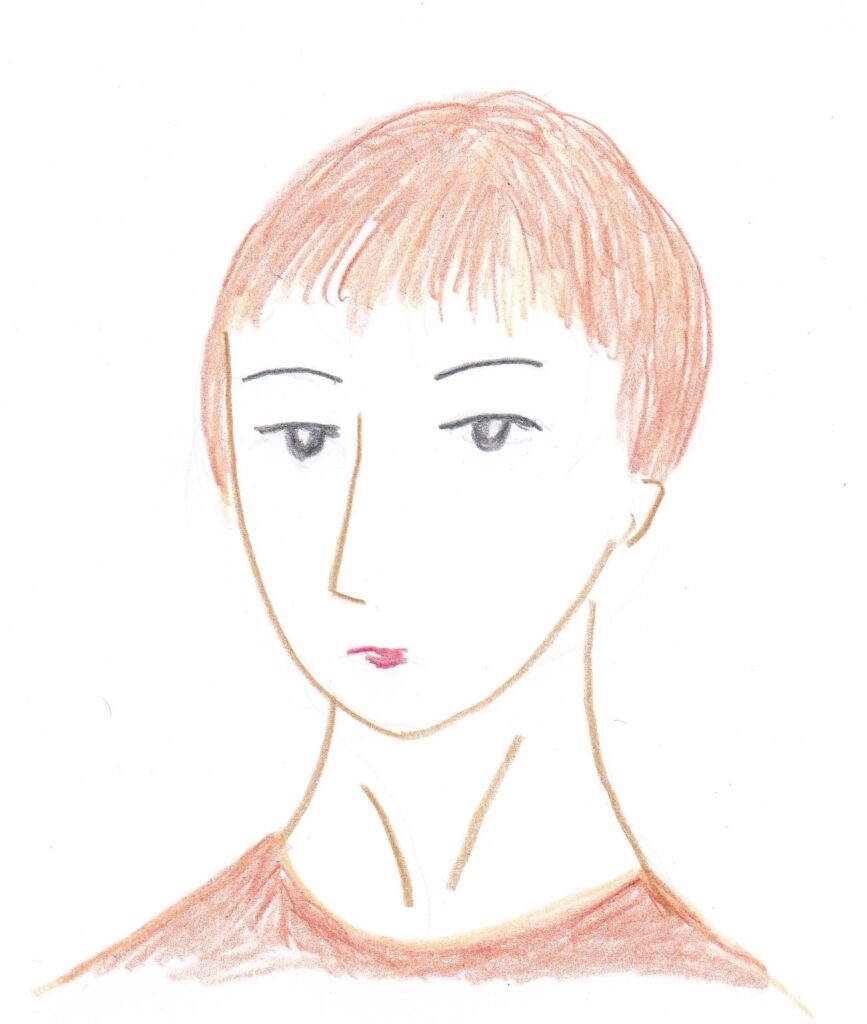
「それでおれ、何か落ちこんじゃってさ」タカヒコネは吐息をついた。
「何が? 何に?」
「あのミズハに、困った人ね、と言われたんだぞ。あの、村じゅうのやっかい者の、何も考えてないいたずら好きの、何でも破壊しまくりの危険人物のミズハにだぞ。もう本当に自分がとことん、だめな人間みたいに思えて。思えてって、事実そうなんだが、きっと」
「おいおいおい」
「理由とか理屈とか言う前に、あの心から哀れむような目つきと口調で、ほんとに、たたきのめされた」
「どうせ、クラド王のお妃が言ってたことを聞きかじってた受け売りだろう。気にしちゃだめだよ。母もときどき父に言ってたような気がする。困った人ねえ、って」
「受け売りだろうが聞きかじりだろうが、ミズハは何も考えてなかろうが、おれは本当に自分がそんな人間って気がしみじみしてしまってさあ」
「よせったら」
「コトシロヌシ」タカヒコネは恨みがましい目で友人を見た。「オオクニヌシはなぜだかいつも、私がとても悲しいときに笑いそうにするんだよな。そして君も、さすがに親子っていうか、同じような目をするんだよ。何がおかしい?」
「誓って何も、おかしくない」コトシロヌシは顔をひきしめた。「ただ、頼むから落ちこむのはよせ。ミズハに返り討ちにされてどうすんだ。しっかりしろよ。キノマタとはちがった意味で、あの子はほんと、手ごわいぞ」
※
「そう言いながら結局おまえも、そうやって笑うんだな」オオクニヌシはさじを投げたような顔をした。「タカヒコネもかわいそうに」
二人は湖のそばの畑で、豆をもいでいた。コトシロヌシは首にまいた布で顔の汗をぬぐいながら、いつもの静かな落ち着いた声で、「いやしかし父上」と言った。「こういうのは連鎖反応みたいなもので、実は私もタカヒコネと話している内、自分のことが変に気になり出して」
「それで畑の手伝いに来たってわけか」オオクニヌシは言った。「まあいい。豆がどうせ余るから、持って行ってくれると助かる」
「ありがとうございます」
「それで、おまえの気になることとは?」
コトシロヌシは手をとめて、ちょっとくすぐったそうに笑った。「私は、いい弟でも、いい息子でもなかったなあと、ふっと、そういう気がしはじめまして」
※
オオクニヌシが今度は手をとめた。ちょっと唇を開いて、彼はいつも冷静で落ち着いている息子を見つめた。
「いや、これは驚いた。それはいったい、どういう意味かね?」
「兄のタケミナカタはいましたが、私自身に弟はいませんでした。まあ今さら言うまでもないわかりきったことですが」コトシロヌシは言った。「そして、妹のシタテルヒメは、これもあらためて言うまでもありませんが、妹と言うような、かよわさも愚かさも皆無でしたし」
「まあ、それはそうだ」
「だから、楽しみを知らなくて。タカヒコネとつきあっていると、なるほど、弟を持つというのは、本来こういう面白さがあるものかと」
オオクニヌシが口をむずむずさせているのを見て、コトシロヌシは首をすくめた。
「遠慮なくお笑い下さい。タカヒコネとちがって私は気にしません。というか、こういうところがいけないんだな。かわいげがないというか、つまらないというか」
「続けてくれ」オオクニヌシは豆をかごに放りこみながら言った。
「タカヒコネの、あのバカバカしい幼さと、次どうなるかわからない危なっかしさを見ていると、私はしみじみ気がつきました。ああ、兄はきっと、こういう弟がほしかったのだな、父であるあなたは、こういう息子がほしかったのだなと。お二人にとって私がいかに冷たく、よそよそしく、ものたりなかったのか、実にはっきりわかって来て」
「いつも言っているだろうが」オオクニヌシは言った。「もぐらに空を飛べと言っても、とんびに土にもぐれと言っても、そんなことはできない相談だと。おまえはそれで充分に面白かったし、頼りになったし、いっしょにいても離れていても、いつも楽しい相手だったよ」
「それはわかっています」コトシロヌシは笑った。「今さら自分が変わろうとも、変われるとも思ってはいません。ただ、どういうか、ありがたくて…彼がいてくれてよかったと。タケミナカタはきっととても幸福だったのだろうと。そして、今のあなたも」
「まあ、それはいいんだが」オオクニヌシは頭をかいた。「問題は、彼が今、私たちほど幸福ではないらしいことだな。ミズハに言われたことで、落ちこんでいるんだろう?」
「変になぐさめても、またどうせ傷つくんでしょうから、そっとしておくしかないですね」
「あれも、強いから、落ちこみながら、やりはじめたことはやめないはずだ。ミズハともどうせまた、関わりつづけてくれるんだろうし。まあ、こうなると、ミズハもまんざら役に立たないわけでもないな。タカヒコネはともかく、おまえまでがそうやって、いろんなことを考えはじめてくれるんだから」
「ささやかなお礼に、今度また、ウガヤに乗せてやりますか。その内育って重くなってしまったら、無理でしょうから、今のうちに」コトシロヌシは言った。「渚なら、万一落っこちても大したことはないでしょうし、けがも溺れもしないでしょうから」(2023.8.18.)
