水の王子・短編集「渚なら」18
第十一話・渚なら

その昔、この沼にはクマノクスビ、アマツヒコネ、イクツヒコネという名の三人の兄弟が住んでいたという。本当の兄弟だったか、ただの仲間だったのかはわからない。彼らは、かつて草原を荒していて、タカマガハラのスサノオに殺されたという怪物ヤマタノオロチが再びよみがえらないよう、切り落とされた首の三つを守っていた。しかし、ヨモツクニのツクヨミによって首は奪われ、ヤマタノオロチはよみがえり、三人の兄弟も殺された。
それから長い年月が流れて、今この沼には、また三兄弟と呼ばれる若者たちが住んでいる。近くの村の住人たちは、彼らをそのまま昔の三兄弟の名前で呼び、彼らもいつの間にか平気でその名を名のっている。
「名前なんてどうでもいいのさ」と彼らは言う。「おれたちは風だ。嵐だ。光だ。波だ。この世をゆりうごかし、そのままどこかへ行くのだ」
彼らはよくしゃべり、よく笑い、乱暴で下品な冗談を投げつけ合う。大小いくつかの皮や木や鉄の太鼓を持っていて、しょっちゅうそれをたたき鳴らして歌を歌う。それがあたりの空気をふるわせる。村から少し離れているので、それほどじゃまにはならないのか、文句を言う者はない。畑仕事の合間にときどき聞きに来て、いっしょに踊る者もいる。
※
沼は一面に氷がはりつめて、夏でも溶けない。太陽の光を浴びて、きらきらとまぶしくきらめき、時にもうもうと冷たいもやのような煙を上げる。冬はその上に雪がつもり、やがてまたそれも凍って新しい氷になる。
昔はふつうの沼だった、とオオゲツヒメは私に語る。かつて彼女は身体中に口ができて、そのすべてから何でも食べる怪物だった。アメノウズメの鏡が割れて、彼女がもとの娘に戻ったとき、沼にはふわふわと季節はずれの雪がふり、やがて氷がはりつめた。
オオゲツヒメは、そのままこの沼に住んだ。沼の氷を割って持ち帰って畑にまくと、作物の出来がいいので、人々は氷をもらいに来ては、代わりに食べ物をおいて行ったり、家を作ってくれたりしたらしい。誰からともなく、この氷が溶けないのはオオゲツヒメがいるからだと言われるようになってきて、人々は彼女を大切にした。三人の兄弟が住み着いたときには心配する者もいたが、むしろ、よそ者を近づけないためには彼らが沼とオオゲツヒメを守った方がいいと、皆は考え始めたのだった。
何より、激しく陽気にとどろく太鼓の音は、聞くだに心がはずんで楽しく、いつか村の単調な日々にめりはりをつけ、活気を与えるものとして、人々の暮らしになくてはならないものとなって行った。
※
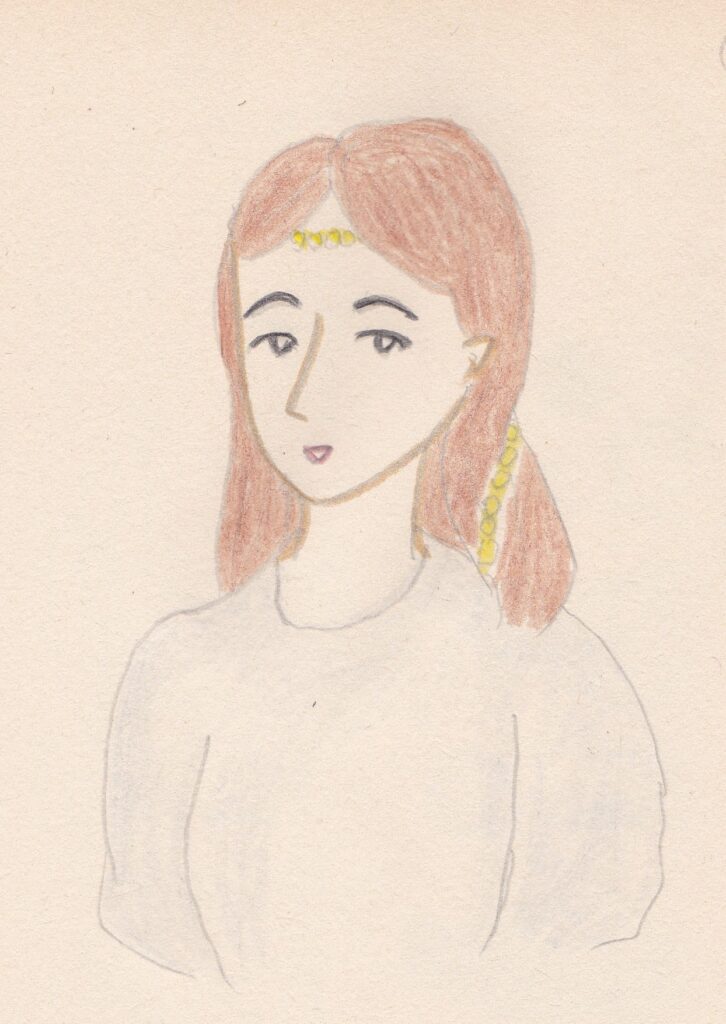
この私、ヤガミヒメも、その威勢のいい、景気のいい音にひきよせられて、この沼に来た。
いつまでたっても赤ん坊のままで育たない一人息子を、その父だった人に渡した帰り、ぼんやり草原をさまよっていて、ふと、その音を聞いたのだった。
かつて王女だった私は、身につけていた、まが玉とひきかえに、一夜の宿や食べ物を得ていたのだが、それもそろそろつきかけていた。
育てても育てても育たなかったものを、ついに手放した空しさと明るさが同時に私を満たしていた。故郷に帰るのも、このまま死ぬまでさまようのも、どちらもそれほどいやではなかった。
けれど、あの音楽を耳にし、きらめく氷の沼を目の前にしたとき、私はここにいつまでもいたいと思った。
そのときに岩陰から現れたオオゲツヒメを見たからというのもある。
色白の、ふくよかな身体。ゆたかな黒い髪、落ちついたまなざし。騒々しい太鼓の音と、まばゆい氷の輝きの中で、彼女はいかにも、暖かく、ひたすらにおだやかだった。
※
彼女のしっとりとやわらかい身体に顔を埋め、ふっくらとはずむ腕に包まれて、今夜も私は眠る。
太鼓打ちの三兄弟は、陽気でがさつで、えげつない冗談が大好きだ。彼らはスサノオがこの沼に立ち寄ったとき、オオゲツヒメが尻や口からごちそうを出して歓迎し、怒ったスサノオに切り刻まれて殺されたという話を広めた。やさしい、きれいなオオゲツヒメが、そんなでたらめな話で語り伝えられるかと思うと悲しいが、彼女は気にせず、面白がっていた。
「そんなことより、あなたの愛した人の話をして」彼女は私の髪をなでて、甘い低い声でささやく。「どんな人だったの? 知りたいわ」
それで私も思い出す。
オオクニヌシ。あなたはいったい、どんな人だったのでしょう?
見るからに手のこんだ豪華な衣装に身をつつみ、それぞれが堂々と自信にみちて、たくましい肩を重ね合わせるように並び立ち、私に求婚した、あなたの兄弟たちの背後に、一人だけ粗末な服でひっそりと立って、私に静かな目を向けていた、まだとても若い、むしろ幼く見えたあなた。
一目見て、やもたてもなく、私はあなたがほしくなった。子どものような無邪気さと、限りない優しさと、そして、かすかな淋しさと。愛らしさと、いじらしさ。兄弟たちの誰よりも大人びているのに、子どもっぽかった、あの清潔な目鼻立ちを、どう表現したらいい?
王女として生まれ育てられ、好きな相手を選べるということが、あれほど幸福に思えたことはない。そのあとで彼を失い、その子を失い、今は何ひとつこの手に残るものはなくても、私は少しも不幸ではないと、心のどこかが知っている。
※
限りなく抱き合い、限りなく語り合った。しなやかに若々しく、感じやすくてみずみずしかった彼の身体も、澄んで、どこやら口ごもりがちな、その声も、私の身体にしみついている。
「平凡な人だったのかもしれません」私はオオゲツヒメに言う。「野望なんてなかった。夢さえも持ってなかった。父や、母や、兄弟姉妹や、他の人たちのすべてとちがって、そういうものに何の興味もなさそうだった。語るのはいつも、身の回りの、目の前の、ささやかなこと。それを心から楽しんで、いとおしんで、満足していた。恨みも憎しみも対抗心も疑いも、まったく持とうとしなかった人」
山の上に行きたいとは思わないんだよ。あの人はそう言った。空のかなたにも、沖のはてにも、行ってみたいと思わない。そうかと言って、今いる村や町や都で、中心になりたいとも思わない。
いつも、どこか皆とちがう。いつも私の心の中は、誰にもわかってもらえない。
けれどいいんだ。だからいいんだ。人とちがって、いつも一人で、それでも私は今いる場所で、生きて、幸せになろうと思っている。そのために、皆のことを知りたいし、回りのことをわかりたい。
※
私と同じか、似た人たちが、空の上か、海の向こうか、どこか遠くにいるのかもしれない。でも、そこに行こうとは思わない。むしろ、ここにいて、そこから誰かが訪れたとき、浜辺で迎えて、ここで暮らすにはどうしたらいいか、少しでも教えて、助けてやりたい。ここの人たちにも、その訪れた人のことを、わかりやすく教えてやりたい。
そのためにも、ここのことをよく知って、皆にとけこんでおきたいし、訪れる人の心もよくわかるようにしておきたい。おたがいに、おたがいのことを、しっかり説明できるように。しばらくでも、ずっとでも、いっしょに快く、暮らせるように。
そうなんだ。空にも沖にも、村の中心にも、私がいることはないだろう。けれどもそれらが交わる場所にいて、やって来る人、出かける人を、幸せにすることは、私にはできる。私にしかできないかもしれない。
波が打ち寄せ、陸と海がふれあう渚なら、私の居場所はきっとある。役割もある。そこに私は立ち続けたい。いつだって、いつまでも。
渚なら、生きられる。
あの人の足もとに広がる砂浜に、いつか潮が満ちて来る。乾いているように見えても、必ず潮はまたよせてきて、あの人の足を洗う。波が砕けて広がって、あの人の指の間をすべって行く。
外では、にぎやかな太鼓の音。
氷をもらいに来た人たちの、笑い声や話し声。
オオゲツヒメのふかふかと暖かい大きな胸にほおをよせて、私はもう、なかば夢の中にいる。(2023.9.2.)
