水の王子・短編集「渚なら」4
第四話・どうしても知りたくて(1)
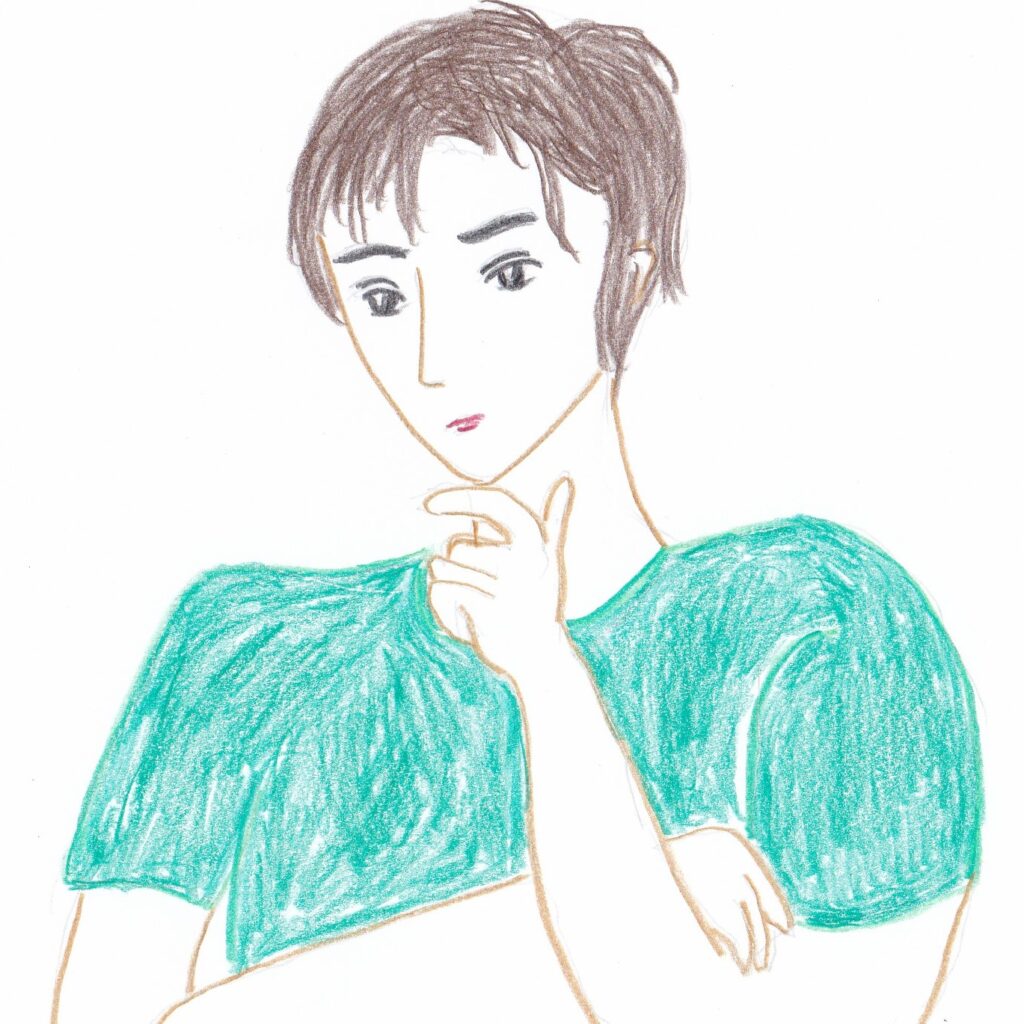
タカヒコネという若者は謎が多い。何よりもふしぎなのは、以前は盗賊で草原で山ほど人を殺したはずなのに、まったく何でもないことを、ひどく恐がる。たとえば、めったにないことだが、私が怒ってきげんが悪いと、本当に緊張して、ふるえる寸前のようにさえ見える。
あまりにあきれて、私も思わず口に出して言ってしまった。
「どうもよくわからんな。君という人間が」
「何がですか?」
「何がって、何をそう恐がってるんだ? 思い出させたいわけじゃないが、大勢の人を殺した男には、とても見えない」
彼はしおれてうつむいていたが、関係ないようなことを聞き返して来た。「あなたは人を殺したことがないんですか?」
「ないな。たまたま運がよかった」
彼はうなずき、まだ目を伏せたままだった。
「それがどうした?」
「おれは、殺せるから。その気になったらいつでも。その気にならなくても、自分を守ろうとしたら、きっと勝手に身体が動く。あなたにとって殺さないのがあたりまえのように、おれにはそれが自然なんです」
私が黙っていると彼は「だから」とつぶやいた。「だからあなたが、そのことで、おれを心配して見張っていても、それは当然なんじゃないかって」
※
「それで、あんなことを考えたのか」私は言った。
ことの起こりは彼が他の若者たちとしゃべっていて、「オオクニヌシは本当に君をかわいがってるなあ」「べたべたに甘いよな」などとからかわれた彼が、反論のつもりか照れ隠しか、「ちがうって。あれは、おれが危険人物だから、村に害を与えないように、しっかり見守っているだけさ」と、カッコつけて言っていたのを聞いたからである。
同じようなことを、たしかアメノサグメも言っていたことがある。まあ人がどう言おうとかまいはしない。しかし本人が少しでもそう思っているとしたら聞き捨てならない。
皆が帰ったあとで、本当にそう思っているのかと問いつめたら、彼はいきなりしょげてしまった。何をとがめられているのかさえ、はっきりのみこめていないようで、ただ私が猛烈に怒っているらしいのを感じて、ふるえ上がっているように見えた。彼はこういう時、無駄にカンがいいのだ。私に対してだけかもしれないが。
※
「ごめんなさい、オオクニヌシ」彼はとっさに謝ってきた。
「父さんと呼べ」私は言った。
これまで一度も、そんなことを言ったことはない。いっしょに暮らすようになってから、かなりたった頃、彼がうっかり私のことをそう呼んでしまい、以後だんだんとそれが普通になってきたが、皆何となく知らないふりをしていた。私たちも、おたがいに。だが、この時は、きっぱりとそう言っておくことが、必要だし正しいと感じた。果たして彼は目をぱちくりさせたが、どこか、ほっとしたようでもある。
「人が言うのは気にしない」私は言った。「だが君が本気でそう思っているなら話は別だ。私が君を大切にしているのは、君におかしなことをさせずに、村を守るのが目的だと、君は感じているのだろうか?」
※
彼は今度は黙っていた。よく考えてみているようだった。
「人からそう言われたら」乾いた声でやがて彼はつぶやいた。「そうじゃないとは言い切れない」
「そうか。そんなら覚えておいてくれ。多分二度とは言わないから」私は言った。「私は君が好きだ。大切だし、愛している。君が幸福で無事でいるなら、この村なんかいくつでも滅びてしまってかまわない。苦にもならない」
彼はうれしそうと言うより、とまどった、悲しそうな目で私を見上げた。
「どうしてそんなに自分が大事にしてもらえるのか、わからなくて」彼はつぶやいた。「それがわからないから、いつまたそれがなくなるのか、見当がつかなくて」
※
少しふしぎだった。彼はもともと、マガツミと言われる、悪の国ヨモツクニの生物である。スサノオの都で、三人の女の手によって、人間として作り上げられ誕生させられた。しかし、それから皆にかわいがられ大切にされ、スサノオにも愛されている。都を改革しようとした若者たちの集まりの中で、誤って敬愛していた仲間の青年を殺してしまい(それは私の実の息子のタケミナカタでもあったのだが。そして息子を殺した者にふりかかるようにしておいた私の愚かな呪いのせいで、今もなお彼の身体は完全に健康を取り戻してはいないのだが)、衝撃のあまり都を離れて盗賊となり、草原で悪事の限りをつくしたあげく、この村に来て、なぜか私に心を許し、慕ってくれるようになった。
どこか野生の動物のような純粋さといちずさで私を好いていてくれるのは、実によくわかる。しかし、そういう相手をいつか失うかもしれない、去られるかもしれないと、それほどびくびくおびえるような記憶や体験が、彼にはどう考えてもありそうにないのだ。自分自身がスサノオや都や仲間を捨てたから、あるいはその後、多くの人を殺したから、逆に自分がそうされないかと恐くなるのだろうか。だが彼の切実な心配のしかたには、どこかそういうものとはちがった、現実的で具体的な、せっぱつまったものがあるように思えた。
※
「私が死ぬとか、どこかに行ってしまうとか、そういうことが心配なのか? まあそれはたしかに絶対ないという約束はできないが」私は笑いながら聞いた。「それとも私が、あっさり心変わりして、好きだったものを嫌いになってしまうような、いいかげんな男に見えるのか?」
「いえ」彼が唇をかみしめたのが見えた。「そんなことない。あなたは逆にしつこい人です。心変わりなんか絶対しない。見限られたらおしまいで、好かれたら何があっても見捨てられることはない。それはよくわかっています。だから、わからないんです」
「何が?」私は少々じれったくなっていた。それがどこかに表れたのかもしれない。悲しそうに、本当に悲しそうに、彼は「キノマタ」とつぶやいた。
「…何?」
「あなたの前でその名を言っちゃいけないとコトシロヌシに言われています」彼は私から目をそらしていた。「あなたが苦しむからって。だから言わないようにしていたけれど」彼は顔を上げ、やっと私をまっすぐ見た。「おれはなぜ、あなたが彼をあんなに相手にしなかったのかわからない。どうしてあんなに遠ざけて、目もくれなかったのか。彼に、あなたに愛されない、どんな理由があったのですか」
私は黙っていた。とっさに何も言えなかった。
「どうしてキノマタじゃなくて、おれなのかわからない」彼の声はふるえていた。「キノマタが与えられるはずのものを、おれが受けとっちまってるような、そんな気持ちがずっとどこかでして。あなたがおれにしてくれているいろんなことは、キノマタにしてやらなきゃいけないことじゃなかったんですか。キノマタにできなかったことを、おれにしてくれてるんじゃないんですか」
「それはちがうよ」私は言った。「それはたしかだ」
「なぜ彼じゃだめだったのか知りたいんです」彼は言いはった。「なぜあなたがあんなに彼をしりぞけたのか、お気持ちがわからない」
彼が身体をこわばらせ、固くしているのがわかった。いつもなら、酔ったらすぐにべたべた私にくっついてくるのに、今は絶対さわらせまいとしている決意が伝わってくる。
油断していたな、と何となく思った。追いつめられたな、ともどこかで感じた。(続く)
