(23)ぺて子
寸暇を惜しむ片づけの中で、まるで得意でも何でもない作業に、思わぬ時間を取られたりする。
田舎の家に山ほどあった、古いうちわを、共謀罪反対のデモの時などにプラカード代わりに持って行ったらどうだろうと、つい出来心で元の紙もはがさないまま、薄く洗濯糊を指で塗り広げて、これも捨てかねていた、いろんな包み紙をはりつけていたら、すっかりはまってしまって、20本近く皆にあげた。私より器用な人たちが、かわいいイラストなどを描いてくれて、ときどきデモに持って来る。しかし、あと二十本ほど古いうちわが残っている。ここまで来たらしあげたいし、めちゃくちゃ無駄な時間のような気もするし、しかし雑念を払う精神統一には、これが案外よかったりする。
私はまるっきり手先が器用ではない。ついでに運動神経も鈍い。それなのになぜか突然、座布団カバーを何枚も縫ったりする。昔はミシンも持っていたが、大きな重い代物で、さすがにこれは処分した。その後は手縫いでちくちくやるが、多分ほとんどの男性よりは縫い目が荒くてふぞろいだ。でもなぜかまだ、この年になって針に糸は昔と同じように通せる。糸の先を斜めに細く切っておいて、だいたいの見当をつけてさしこめば、ほぼまちがいなく成功する。
適当な大きめの紙箱に入れた裁縫道具は古びていて、針山の針は少し錆びている。それをそのまま使っている。小学校のとき、家庭科で使うのに、かわいいプラスティックの裁縫箱を買ってもらったのだが、私は母たちが「かわいいねえ」と満足して買ってくれた、たしか緑の地にこけしが一つついただけの、すっきりしたデザインが嫌いで、友だちの皆が持っている、花や何かがごちゃごちゃと描かれた普通の模様のがほしかった。そのせいか、裁縫道具にはまったく執着がなく、たしかその後念願のごちゃごちゃしたいかにも普通の裁縫箱も持っていたような気がするが、今はどれもなく、まるで記憶に残っていない。
多分、大学時代だと思うのだが、高校時代だったかもしれない。そんな私が人形を作った。
小さい時、私はかなり大きい「ぺて子」という名の人形を持っていた。これは叔母の手作りで、叔母もまた私と似て、決して器用ではないのに、突然そういうものを作ってみたりする人だった。ぺて子の顔も服も私は全然覚えていないが、かわいらしいというより無気味な顔で、第一母がみっともない、下手な出来だとバカにしていた。そう言いながら私にそれを持たせてくれていた母も、特に愛着はないし、嫌いでもないのに、何となくそばにおいていた私も、それを特に残念がりもせず、私にぺて子をかわいがらせる、それ以上の工夫や努力も特にしなかった叔母も、三人三様、今考えると投げやりなのか遠慮していたのか、よくわからない。私がぺて子で覚えているのは、その大きさと、名前だけである。
小学校に入るころには、ぺて子はもうどこかに行って見えなくなっていた。今考えると私は子どものころ、木製の大きな立派なトラックも二つ持っていた。これは立派な作りで、一つは緑と黄色、一つは赤と紺だった。そこそこの値段はしただろう。ジェンダー教育と言う点では先進的と言いたいが、あまり何も考えずに誰かが買って来たのだろう。私はこれに、積み木などを積んで押したり引いたりしていた。ぺて子よりは後まであったが、それもどこかに行ってしまって、今はない。
ぺて子の後に長いこと私が持っていた人形は、母と文通していた、アメリカの女性が送ってくれた灰青色のつややかな衣装を着て、あおむけにすると目を閉じる美しい人形だった。母は英語の教師の免許を持っていて、近くの子どもたちに教えたりしていた。その英語の練習もあったのか、多分雑誌か何かで募集したペンフレンドの何人かと文通していて、ドイツやアメリカから小さいプレゼントが時折届いた。小さな匂い袋や、カードなどで、そのどれからも、清々しい不思議な異国の香りがした。それは今でも、いわゆる舶来品に共通する独特の香りだが、なぜか私が多くの飼い猫の中でも一番好きだった、八歳でエイズで死んでしまった大きなオレンジと白の牡猫が、最期はやつれても死ぬまで毛はきれいで、いい匂いがしていて、それが小さい時からなぜか、この舶来品の匂いだった。私は彼の首筋に顔を埋めては外国に行った気分になっていたものだ。
そして、小鳥と庭園の絵が描かれたカードの一束は、見るたびに美しすぎて、やるせない淋しさと激しい悲しみさえも生んだ。幼い私は、部屋の隅で、そのカードを見ては、あまりにも美しい世界は、どこか悲しいものだと知った。そこに行きたいというあこがれが、そうさせるのかもしれなかったが。

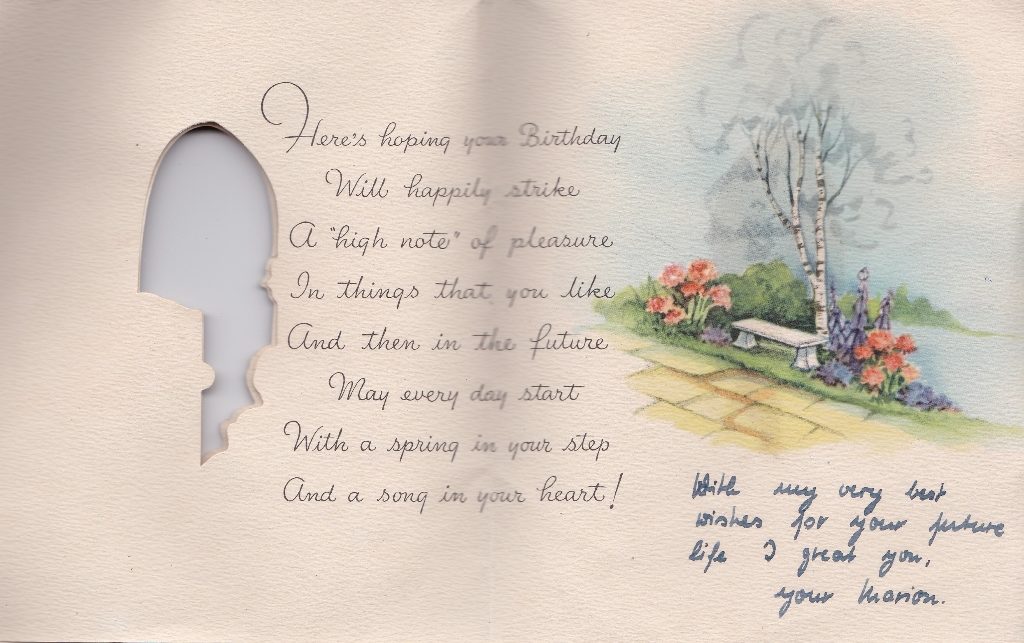
私は小学校の友人と、その灰青色の優雅な衣装に身を包んだ人形が悪人にさらわれて救い出すという冒険ごっこをよくやって、人形の金髪にかぶさった帽子の長いリボンで、彼女を縛ってさるぐつわをしたりしていたから、どう考えてもあまりまともな子どもではない。だが、そのきゃしゃで美しい人形は、そういうことをされると、変に似合って魅力的だった。
DV夫の言いわけめくが、私はそんな虐待をしながら、その人形は大切にしていて、汚しも壊しもしないまま、ずっと後まで大事にしていた。そう言えばふしぎなことに、なぜか名前はつけなかった。まあ、ぺて子だって、私がつけた名ではないが。
その人形もいつかなくなり、多分誰かにやったのだろうと思うが覚えていない。
叔母の継子にあたる従姉が、目のくらむほど豪華でたくさんの人形の家の家具を持っていた。彼女自身が人形のように美しく、私はあこがれるとかうらやむとかいう感情抜きで、たとえば庶民の小娘か召使いが王女や令嬢を見るように、完全にちがう次元の人として仲よく遊んでいたので、そういうものを見てもほしいという気持ちはまったくなかった。ところが彼女はある日突然、それを皆あっさり私にくれてしまった。
私はもちろんうれしくて、これまた、離れの出窓にリンゴ箱を並べて、その家具を配置し、それに合わせた小さな人形のいくつかで、さまざまな小説を題材に芝居をして、小学校の親友に見せて遊んだ。それは毎回ものすごく長い時間で、よく友人はつきあってくれたと思う。
ところがこれまた、私は多分中学のころか、まったく突然つきものが落ちたようにいきなり熱が冷めて、従姉がしたとまったく同じように、その人形の家具一式を、十歳ほど年下の知人の娘さんに全部あげてしまった。私がそうしたと同じように、彼女も喜びつつ、ごく自然に驚きもせず、もらって行った。
私は子どもが成長して幼年時代を捨てるという考え方が、実はあまり好きではない。結局世間の常識の枠にはまるに過ぎないことが、そう表現されることも多いからだ。だが、従姉と私と、その年下の女の子とのことを思うと、もしかしたら、あの人形の家の世界のようなものは、ああやって、ひとりでに自然に次の世代へ引き渡されて行くものなのかもしれないと思う。ぺて子や灰青色の衣装の美しい人形も、いつの間にかそうやって、自然に私の世界からどこかへ退場したのかもしれない。
さて話をものすごく元に戻すと、そういう人形たちのこととはまるで関係なく、多分忘れていた中で、すでに大人になりかけていた私はなぜか人形を作った。
作った心境も全然覚えていないのだが、もしかしたら、その人形の家具をくれた従姉が、すべておしゃれな少女で、多分、当時少女たちの流行の先端だった「それいゆ」という中原淳一の少女の顔が表紙の、横長の雑誌を何冊か私にくれて、その中に「雪んこ」という人形の作り方があったのを参考に、いくつか人形を作ったことがあって、その余波だったのかもしれない。最初に作ったいくつかは、あまりいい出来ではなく、手元においてはいたのだが、これまたその内、どこかに見えなくなってしまった。だが、その時に人形を作る基本的な方法は覚えていたのだろうと思う。
ありあわせの、古い茶色の布で作ったのだが、その人形は多分まったく偶然に、なかなかの出来だった。頭は何だか平べったいが、黒糸と赤糸で刺繍した眉と目と口もよい表情にしあがって、古いオレンジの毛糸でつけた長い髪も茶色の肌によく似合った。
この人形にも私は名前をつけなかった。特にかわいがるでもなく、もしかしたら田舎の家にずっと放りっぱなしにしていたかもしれない。
大学時代の友人がこれを見て、気に入ってほしいと言ったときも、大して未練もなく渡した。もうその時点でかなり古びていたような気がするし、そもそも私はこの人形に服さえ着せていなくて、ただ白い布の胴体に「m」とか「y」とか、今ではまったく謎としか言いようのない文字を赤のマジックで書いていただけだったと思う。
その友人とは、いろいろまったく性格も好みもちがうし、たがいに気づかずものすごく傷つけあっている気もするが、なぜか今でも一番の最高の親友である。もっともあっちもそう思っているかどうかは知らない。
彼女の家にも一度しか行ったことはなく、お母さんとも多分お会いしていない。そのお母さんは、この人形に立派な布地で服を作ってくれ、髪も短く刈りこんでイメージチェンジをしてくれた。
私は彼女と特に理由はないが、ずっと会ってなかった時期もあり、人形のことも忘れはてていた。何十年かたって、私の勤務先が彼女の故郷に近くなったこともあって、わりとよく行き来するようになってから、彼女はその人形のことを思い出して返してくれた。彼女のお母さんはもう亡くなっていたが、上品でしっかりした人形の服はきれいなままだった。
せっかく返してもらったのに、私はその人形をまたどこかに押しこんだまま忘れていた。それから多分また十年以上たって、人形は髪も服も虫に食われたのかぼろぼろになり、顔や手足の茶色の布も劣化して汚れた。奇跡的に無事に残った顔の眉や目や口も、すっかり色あせた。
何とかしてやるかと思って、しかしもうずっと裁縫などしたこともないので、なかなかその気になれなくて、ただ、荷物を片づけていると、母が使った毛糸がたくさん出て来るので、このどれかを新しい髪にしようと思う時期がずっと続いた。
ちなみに母はかなり年をとってから、近所の奥さんたちと、編み物のパートに精を出していた。私が帰省すると、サイズが一センチでも狂うと返品されるのよ、おかしいと思わないね、少し大きいのや小さいのがほしい人だっているだろうに、とぼやきながら、赤ちゃん用のかわいい服をものさしで測っていて、「あんたも手に職をつけていた方がいいよ」と、曲がりなりにも大学教授で本も何冊か出している私に真顔で忠告した。最終的には編み機まで買って、青と銀の美しいレース糸で自分のワンピースなども作っていた。
編み機はもちろん処分したし、たくさん残っていた毛糸もまだ新しいから人にさしあげた。私が人形の髪にしようと思っていたのは、もっと大昔の、太い古い毛糸の玉だった。ひょっとしたら祖母が使ったものかもしれない。集めたらそこそこの量になったので、網の袋に入れて仏間の壁にかけて飾りにしたが、その中のどれかを新しい髪にしてやろうと思ったのである。
この忙しい時に、と千回も自分にぼやきながら、ある夜テレビでDVDを見ながら私は人形の再生にかかった。何しろ布が古くなっているので、髪や服を留めた糸を切るだけでも、破れはしないかと気が気ではなかった。
数日かけて、ものすごく適当にだが、髪は何とか新しい茶色と黒の毛糸玉二つを使って、ふさふさと豊かにつけた。だが洋服はうまく行かない。手芸品店で端切れを買ってきて、切りこまざいてくっつけても、どうもいまいち、ぱっとしない。それではとスーパーで乳児の服を買って来て着せてみたが、当然ながら微妙にサイズが合わなくて、修正しても無理そうである。
いやになって、しばらく投げ出していたときに、未整理の衣類の中から、叔母の古い下着が見つかった。
叔母は洋服も多かったが、下着も見るからに美しい高価にちがいないものをそれこそ山ほど残して死んだ。それでもパーキンソン病で病院で亡くなる最後には、診療に便利なようにと味気ない灰色の縞のパジャマや、野暮ったい下着を着せられていて、私は結局最後はこうなるのかと、妙に諦めがつき覚悟ができたものだった。
叔母の遺した下着は母に使わせたが、田舎暮らしの母はスリップなどは着ることがなく、パンティも時に失禁して汚したら、そのまま捨てていたようで、あまり有効に楽しんでいたとは言えない。更に年を取って一人暮らしが無理になり、老人ホームに入ってからは、最初は叔母のその美しいインナーを着せてもらっていたが、幅広のレースが山ほどついた繊細な生地は、職員の人にも扱いにくいような気がしたし、マジックで名前を書くのもしのびなくて、結局私が使うことにした。
ちなみに母の、その施設で着る服にも、それなりに苦心した。叔母と同様、母も華やかで鮮やかな色の服が好きで、黒や灰色は見るのも嫌いだった。だから私はせいぜい若い人向きの派手な色のTシャツや大きな柄のセーターを買って、クローゼットに入れていた。
ところが、そういう若い人たちの服というのは、たいてい喉元が大きく開いているから、下着が見えてしまう。また、冬は冬でTシャツやセーターの上から重ねてかぶる大きなセーターにおしゃれなものが多いのだが、職員さんたちは忙しいのか、重ね着はまずしてくれない。首の広く空いた派手なざっくりしたセーターを着て、寒々とした様子の母を二三度見て、私はあわてて、この種のセーターも皆回収した。以後、夏も冬も適度に喉元のつまった、おしゃれなTシャツやセーターをさがして街をさまよい歩くことになり、その癖は今でも残って、タートルやハイネックの素敵な服を見ると、本能的にすわっと飛びついてしまい、あれ?とワゴンの前で首をかしげたりしている。
ついでに言うと、フリースのかわいい模様の小さい毛布は安いし肌触りがいいので、私はよく母に買って行って、枕や襟もとに敷いたりかけたりしていた。ところがこれまた、その施設ではお花見やお食事によく入居者を連れ出してくれるのだが、そういう時にクローゼットにジャケットやコートやカーディガンをいくつも入れていても、なぜか母だけは、そのフリースの毛布を肩に巻きつけて、何だか哀れっぽい姿で連れ出されているのだった。そういう行事の時の写真は、まめに撮って壁に張りだしてくれるので、わかるのである。母は入居して間もない、意識もはっきりしているころはよく、自分の派手な服装につられて、他の人たちも赤い色や花模様の服を着始めたよと笑っていたりして、実際にその写真で、皆の服装がけっこう華やかなのを見て私もひそかに喜んでいた。
それだけに、ちゃんと毛皮のジャケットなど羽織ったお年寄りの中に、薄っぺらいフリースをぐるぐる巻きつけられた母の写真を最初見た時はショックを受けて目まいがし、これは母がいじめられているのかと被害妄想に陥りかけたが、もちろんそんなはずはない。そこの施設の人たちはおおむね皆とても行き届いて礼儀正しく親切な上、母はけっこう好かれてもいた。
あれはやっぱり、そのフリースがかわいいし軽くて暖かいので、使ってあげてみたいという、職員さんの素直な好意であったとしか思えない。それにしても、それはやはり、ちょっと悲しい格好だった。これまた私は自分が年とって入居したら、どんなとんでもないファッションをさせられるか、選べないしわからないなと、覚悟を決めた。本当にいろいろ覚悟を決めておくことが多いのである。
それにしても母が入居した最初のころにフロアの担当者だった職員は、服の選び方も組み合わせ方もものすごく上手だった。私が思わずそれをほめると、デパートの服飾部門で働いていたということで、なるほどと納得したものだ。その人がいなくなってからは、これも決して悪意ではないのだが、悪意じゃないかとときどき疑うほど、とんでもない模様入りのパンツとセーターを組み合わせたり、これだけは絶対しちゃいかんだろうというような取り合わせの上下を着せてあったりした。
もっとセンスを磨けなどという要求ができるはずもないから、私は自衛手段を考えた。パンツは色は派手でも無地なものにして、他の服も、何と組み合わせてもいいような、しかも個性豊かで良質のものを選ぶ。むろん、えりもとは詰まったもの。かくして母の服選びは、ますますハードルが高くなり、ものすごい判断力と選別力が要求され、高級デザイナーなみのセンスを私は日夜磨くはめになった。もちろんフリースの毛布は皆回収した。
そういうわけで、叔母の美しい高級下着は私が結局独り占めした。こればっかりは、そうそう人にも上げられない。
しかしこれがまた、品物が良い上に多数をとっかえひっかえ着るから、なかなか古くならないし、まだ一枚も処分できない。とはいえ、年に二回ほど観劇に行くとき、めったに着ない叔母の高級ワンピースを着てストッキングをはき、これでもかというほどレースのついた、するするとなめらかなスリップをまとうと、やはり心が引き締まるし、やる気になる。
どうしてか昔から私は、会議やその他で誰かと大喧嘩する時には、こういう服装をするのである。もっと最高にのるかそるかの大勝負をする場では、ヒールのある靴をはいて、更に一大決戦だったら化粧をする。観劇はちがうが、基本的にこういう服は私にとって戦闘服で、その気分を思い出させる小道具としては高級下着も悪くない。
しかしだ、もう一つ言うと、母のを回収したのも私が買ったのも、今のTシャツやセーターは襟ぐりが大きく開いているのは共通で、普通の下着だとやっぱり少し見えてしまう。いかに叔母のインナーがレースつきの上等でも、それはやっぱりまずい。
数年前から私はもう、夏の下着は買わないで、タンクトップですませている。それなりに、ちょっとおしゃれで上等のものをそろえておけば、そのまま出かけられるし、襟元からのぞいてもいいし、都合のいいことこの上ない。
そういうわけで叔母のインナーは、ますます、ここぞという場合しか、身につける機会はなくなるのである。
叔母は私よりやせていたから、ガードルなどは窮屈なのだが、それでも無理をして私は使っていた。品がいいから、よく伸びるのだ。
だが、さすがにこれはもう捨てるしかないかなと思って、でも未練がましく洗濯機のそばのかごに入れっぱなしにしていたのは、総レースのようなやわらかい白いキャミソールだった。何しろ胸元にブラジャーが縫いこまれているから、いかに私でもどうにもならない。そう言えば叔母のブラジャーはまったく手元にないが、誰かにあげたか、叔母は使っていなかったのだろうか。
で、その下着で人形の服が作れないかなと思った。もう脱ぎ着させるのは諦めて、下着代わりに胴体に縫いつけてしまえば、私でも何とかサマになるのではないかという気がした。
さっそく、はさみでボディの部分を切り取って、縫いつけてみたら、下着というよりウェディングドレスのようで、行けそうである。気をよくして、私は肩の部分も切って肩や背中に縫いつけた。さらに最後に残った、捨てるつもりだったブラジャーの部分を、ケープのように襟もとに留めつけてみたら、これがまた、案外かわいい。
もちろん私の仕事である。針目もがちゃがちゃ、切った端の始末もろくにしていない。
しかしまあ、どこにもないということでは貴重品だし、何より叔母の上等の下着を捨てずに有効利用でき、その生地の美しさと高級感も立派に活用できたことで、私は大いに満足した。



すっかりよみがえった人形は、今、仏間の古い椅子に昔のままの、考え深い、ちょっと悲し気な顔で座っている。
ついでにもう一つ、これはずっと最近、と言ってももう三十年ぐらい前、主婦の方々と紀行文の研究会を毎週させてもらっていた、近くの駅前のおしゃれな喫茶店で、ある時近くの作家さんの人形展が行われて、ちょっと風変わりなピーターパンのような人形を買ったのを、やはり放っていた間に、片方の目のフェルトがはげかけていたのも補修した。
その作家さんの娘さんが別のご縁で私と知り合いとわかって、もう一つきれいな色のピエロの人形も後で下さったのだが、それは誰かにプレゼントしたようで、もう手元にない。例の私のくせで、きれいな方は人にあげて、こちらを残したのだろう。
手芸用品店でフェルトを買い、フェルト専用の糊というものも買って、こちらは比較的簡単に目はちゃんと元通りになった。
これも仏間の、昔祖父が村医者をしていたとき、診療に使っていた肘掛け椅子に座っている。プロが作ったものだから、私の荒っぽい手作業の人形とは比較にならないが、写真などで遠目に見ると、さほどのちがいはないように見えるのが、ちょっと笑える。
この人形にも名前はない。
叔母の下着を着ていることでもあり、私の手作り人形の方には、顔も覚えていない私の最初の巨大な人形をしのんで、ぺて子と名前をつけてみようかと、ちょっと思ってみたりしている。(2017.7.10.)
