『大才子・小津久足』感想(18)
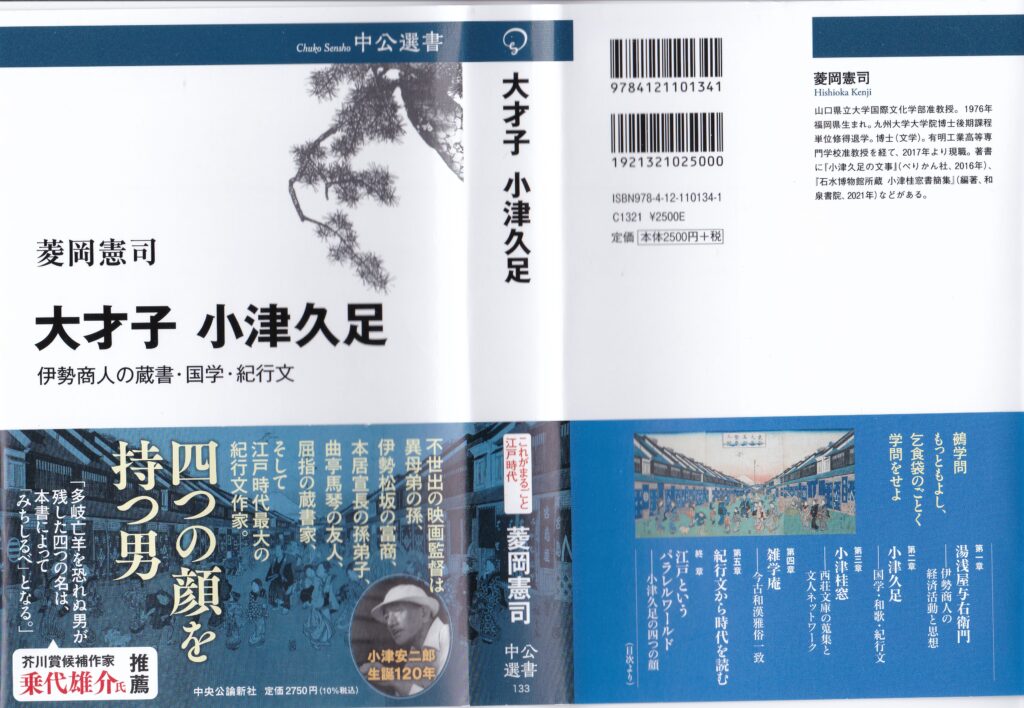
【私には江戸時代はわからない】
まずは、江戸時代について。
この第五章の最後すなわちこの本のしめくくりに、菱岡君は私たちがどのように江戸時代と触れ合っていくかについて述べている。
現代の感覚を基準にして見るのではなく、あくまでも江戸時代の人の心になってその時代を理解しようとすること。
いたずらに理想的な世界と美化するのではなく、もちろん暗黒の時代と断罪するのでもなく、今の私たちとの共通点だけをさがすのではなく、異なる点も理解して、うけいれること。
そのために、小津久足という人物と作品を通して、ありのままの江戸時代を知ることが可能になるだろうこと。
これは、菱岡君がこの本のすべての部分で追求してきたことの目的地であり、終着点である。たくさんの糸がたぐりとられて、一本の大きな綱となり、やがて広い織物になって行くのが目に見えるようだ。
ここで菱岡君が語る、江戸時代とのあるべき関わり方は、他の大学や研究機関はどうなのかよく知らないが、私や菱岡君が学んだ九州大学では鉄則であり常識であり前提だった。中村幸彦先生が常に説かれ、中野三敏先生も講義や著書の中で折にふれて強調されていたことだった。近世文学以外の先輩や院生も、これを基本に学問にとり組んでいたと思う。
菱岡君は私の知る限り、決してこの考え方や感覚をうのみにしたわけではない。吟味し、点検しながら自分のものにして行ったのだと思う。そして久足の研究を通して、それを確信として育て上げ、この本の結論として記した。そのことを、わずかなうらやましさもこめつつ、私は喜ぶし、これからの彼の研究の力強い基礎が築かれたことも感じる。中村、中野両先生の説かれたことは、今後、彼の研究を通して、広く深く世の中に定着して行くことだろう。そうであってほしいと願っている。
だが私には、菱岡君の、ひいては中村、中野先生のこのような考え方が正しいのかどうか実はまだわかっていない。まちがっているとは思わない。だが、それを自分のことばで人に語ることが私にはまだできない。実際、授業でもその他でも、私は中村、中野門下生として、何よりも語らねばならぬ、このような江戸時代観を、まだただの一度も自分の見解として口にしたことはない。何だか自分であきれてしまう。
菱岡君がこれから大いにこのような江戸時代の認識を広めて行ってくれることを期待し、ついでに安心して、私自身はもうしばらく、逡巡と混迷の中にいようと思う。
私には江戸時代がわからない。その前に私自身がわからない。
最後の最後になって、いきなりのっけからとんでもないことを言い出してしまったので、混乱された方もおられよう。息抜きのつもりで少し別の話をする。
江戸時代が封建制度や身分制度にしばられた悪の時代という認識は、私の子どものころには学校教育では普通だった。学生たちに聞いてみても、今はもうかなり変わっているようだが、それでも、どってことない黄表紙みたいな表現を、幕府への抵抗という教材にして教えているようなことは、時々見かける。私自身は授業をあまりまじめに受けてなかったからか、特に「江戸時代は悪」という認識はなかった。先生たちもそのことを、あまりというか全然熱心に教えてなかったような気がする。
むしろ私の回りでは、田舎だったこともあるだろうが、敗戦どころか明治維新もあったんかいと疑いたくなるほど、昔ながらの愛国心や日本礼賛があふれていて、そっちに私は子どもながらにうんざりしていた。まあそれは、家に来る新聞や週刊誌の戦後民主主義の熱烈な鼓吹に私が染まっていたからかもしれないし、中村、中野先生が、ほとんど一生をかけて戦っておられたのは、そのある意味軽佻浮薄で時代に迎合した戦後民主主義に基づく文学観や江戸時代観だったのだろう。「娘が『お父さんは封建主義や』と言う。学校で習ったらしい。封建主義はとにかく悪いもんやということになっとるのや」と中村先生は別に悲憤慷慨の気配は全然なく、面白そうに、楽しそうに話されたことがある。
その結果、最近では江戸を理想化して持ち上げるような流れもまた強くなってきた。それは中村先生たちの努力が実を結んだということだったかもしれないが、その中のひとつふたつをとり上げて、思い出すことどもを書いてみる。
【怪談「江戸しぐさ」】
一時期「江戸しぐさ」という用語がメディアでもてはやされた。そんなの聞いたことがないと思っただけで、特に興味もなかったから私は気にしなかったし、周囲の研究者の中でもまるっきり話題にはならなかった。
今、あらためてネットでちょっと見ると、相当にひどいデマということが察せられるし、こんなことばがいっちょまえに横行したということが今となっては信じられない。リンクした記事でも「専門の学者(私もそのはしくれだろう)の否定や反論が全然なくて、それは、あまりにバカバカしいからまじめに否定するのもアホらしいからだ」と書いてくれているが、今あらためて私は、あれだけ世間にこれだけひどいインチキ江戸知識が広まったのに対して、何も反応しなかった私たちに、責任のようなものを感じてしかたがない。
社会的関心のなさ、象牙の塔のプライド、みたいな言い方で説明できる部分もあるかしれないが、それだけでもないかもしれない。学会発表でも論文でも、あまり大きなまちがいがあると誰ももう指摘はしないで放っておく、という傾向が専門家の中にはたしかにある。以前どなたかが「玉くしげ」という本について、「玉くじけ」という表記になっているものもあるということを学会で発表された。古い文章では濁点は普通に一文字上や下に移動するというのは、多分初歩的な知識だが、そのことを誰も質問しなかったし、中野三敏先生などは、あとで「くじけてるのは、あいつの玉なんじゃねえの」と冗談を言っていて、似たようなまちがいをやりかねない私は、血が凍る思いがしたものだ。
しかし、このような冷たさや厳しさは、いったい正しいのだろうか。適菜収氏のブログだったかコラムだったかのタイトルに「それでもバカとは戦え」というがあって、見るたびに妙に納得し、戦っていないかもしれない自分が不安になる。「江戸しぐさ」の用語はいつの間にか聞かなくなった。それでも多くの人の頭や心にはどこかで残っているのではないだろうか。私たち専門家が、真剣にバカと戦ってほろぼさなかったせいで。
前にもどこかで書いたが、年取った母や、若い学生たちに、帰省の予定や試験の期日や、その他もろもろの情報や知識をいったん口にすると、あとでどんなに訂正しても最初の誤情報を完璧に消すことは絶対できない。自分もいつぼけるかもしれないから心しておきたいが、「上書き保存」という作業はものすごく難しく、老化や注意散漫だと、まずこの機能が衰える。だからこそ、教師や政治家、研究者などは、誤った情報や知識を絶対に口にしてはならない。一度言って流したが最後、もう完全にそれを消すことは永遠に不可能だ。訂正しても謝罪しても、取り返しはつかない。それを思えば、「江戸ことば」もしっかり消しておこうとするべきだったように思えてしかたがない。
【ちょろっと予告】
引き続き、これは「江戸しぐさ」なんかとちがって、ちゃんとした本である渡辺京二『逝きし世の面影』と、私の昔書いた『江戸を歩く』について話したいが、長くなりそうだから、明日にでも。
