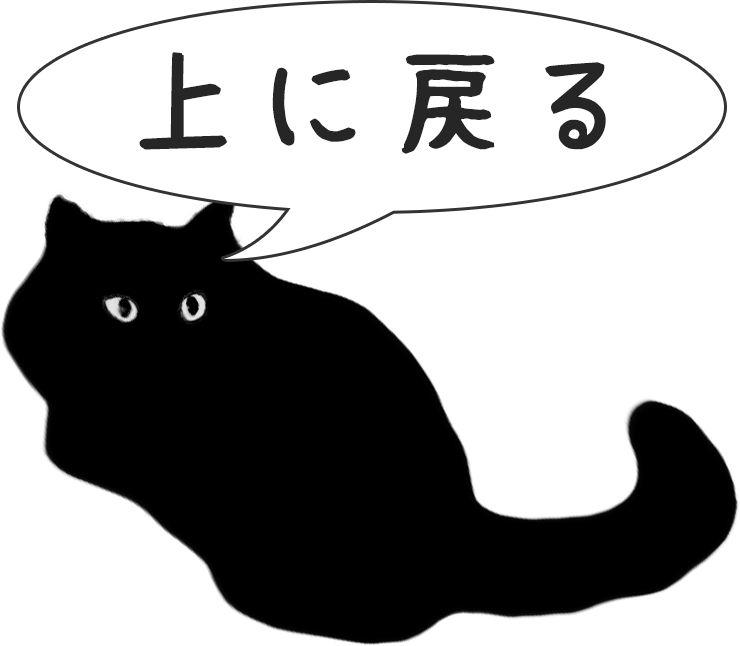もうすぐお別れ
ホークスが何十年ぶりとかの開幕三連敗をするのを横目で見ながら、のんびり一日を過ごした。リチャード選手もヒットを打つし周東選手も盗塁を成功させるし、他の選手も一応活躍してるのに負けてしまうというのが不思議で、悲壮感も少ない。ロッテがよっぽど強いのか、甲斐選手や栗原選手がいない祟りかしらん。そんなこんなで、こっちも決死の覚悟が足りないのか、家の片づけも庭の手入れも、進んでないわけではないが、目に見える効果が出ない。人が見たら、どこがどうどれだけ片づいたのか、さっぱりわからないだろうという基準で、まあ前進はしてるんだけどね。
久々に買いこんで来たひまつぶし用の文庫本を、ちびちび読んでは楽しんでいる。『猫の客』はフランスでも愛読されたらしいが、隣家の猫との交流とともに、借家での生活と、その母屋の静かに年取っていくさまが、繊細で格調高くて静謐で胸にしみる。新しい優しさと、古めかしい純文学のような厳しさが入り混じって、救われるような一方、心の深部まで貫かれるような淋しさや痛さも味わう。すっごくわかるけど、こんな風に感じやすく生きたくはない、もっとがさつに晩年を送りたいと変な逃げの姿勢にもなる。
自分のものではない猫を愛してしまう生活も切ないが、飼い主の家にとっては、それもそれできついのかもな。最後が小さくミステリアスなので、ひょっとしたら三軒目か三人目の存在があったのじゃないかと、ふと思えてしまったりもする。
フランス語に翻訳した方のあとがきで、外国人が日本の文化や風土がわからないという内容のエッセイに昔(まあ今も)強く反発したという部分を読んで、あっと思った。私も高校のとき、受験問題集に出ていたその一文にものすごく異和感があって、マジでもう嫌いだった。小林秀雄の文章だったのか、知らなかったけど。後に授業用のテキストに使って、学生の一人から「そんなこと言われても」と小レポートで疑問を呈されたけど、びくともしないというか、気にもならず聞く耳も持たなかった。そのくらい嫌いな文章というか姿勢というか感覚だった。(ああ、これですね、授業ノートの中にありました。冒頭に出て来ますので、よろしかったら、お読み下さい。)
「猫の客」はすごく日本的だけど、同じぐらい外国の香りもする。フランスでヒットしたというが、イギリスなどでも受けるんじゃないのかな。
ところで愛猫キャラメルの命日は三月初めだったのだが、つい月末まで引き伸ばして、写真を飾って、供え物をしていた。昨日新しい真っ赤なバラといただいたストックを手向け、今日は最後に好物のカワハギを似たのを供えた。明日には普段のかたちに戻して片づけて、カワハギを煮たおつゆを味噌汁にして朝食に加えることにしよう。


大河「べらぼう」は今夜も面白かった。このドラマのいいとこの一つは、立派なお屋敷でも何でも、灯りが弱くて夜が暗いことだ。それが妙になつかしい。俳優陣はあいかわらず皆いやんなるほど達者だし、春町や喜三二につぐ京伝の登場も、イメージが合ってるかどうかは知らんが、妙に笑ってしまって楽しかった。私の大好きな黄表紙(青本)の、「辞闘戦新根」(ことばたたかいあたらしいのね)が、ちょこっとクローズアップされてたのも嬉しかった。これって、今で言うなら、「ダサい」とか「知らんけど」とかの流行語が皆、擬人化されて活躍する話なんだよね。春町って、やっぱ本当に発想が変だわ(ほめてる)。