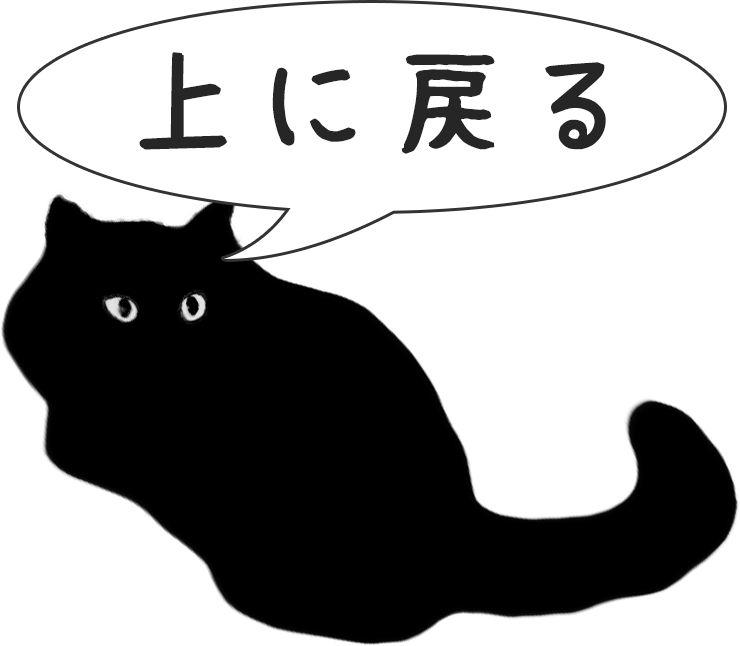吉原細見
大河ドラマの「べらぼう」、今夜も面白かった。今とちがって薄暗い夜の景色のなつかしさと物悲しさと美しさの映像が身にしみた。蔦重役の横浜流星のつるつる軽い雰囲気が、江戸っ子風で悪くない。暑苦しくないパワフルさが、現代の若者にもどこか通じているような、それでいて、もっとしたたかなような。爛熟して何でもありの、江戸後期が流れるように自然に見ている者の中に入って来る。平賀源内の同性愛も、お洒落で切なく、堂々と描かれているのが快感。俳優さんたちは大変だろうが、切れ味のいい早口のしゃべりあいも、小気味がよく耳に優しい。
ほめすぎかな。でも私、もともと江戸時代が根本的に好きじゃないんだよね。つきあいが長いから、なじんでるだけで。だからかえって、点数が甘くなるのかもしれない。
今さらむしかえすのも大人げないが、去年の大河ドラマをどうしても見る気になれなかったのは、「成人した女性が人前で顔をあらわにすることはない」という、大原則の常識がまったく無視され、あえてそうした理由も示さず、日本全土がフジテレビの女性アナ人身御供問題もどきに、口をぬぐって専門家もマスメディアも作者側も黙殺し隠蔽(とあえて書きます)しつくした気持ち悪さと違和感に吐き気を催したからだった。大人の男女が真っ昼間、ほこりの舞う道のまん中で顔もあらわにしゃべって話してかけずり回るなんて、どこの国の平安時代だとしか思えなかった。今年の大河ドラマは今のところ、吉原も男色も、そういうでたらめはしていない。
ところで、貸本屋が広げてる本の中に、ケバい緑色の本が時々見えるのは、あれはいわゆる「青本」かな。
名前としては残っているのだけど、実際には青い表紙の本は残ってない。赤本、黒本、黄表紙はちゃんとあるのに、これは謎だ。日本では青も緑も「青」と呼ぶから、多分当時は緑色だった「青本」が色あせて黄色になって今残ってるんだろうということになってるのだが、まだ真相はよくわからない(はずだ)。
綿密な時代考証はしてるだろうから、きっとあの緑色の本が青本ということになってるのだろう。あんな色の本は今はどこにもまったく存在しないけど、そういう解釈もまた面白い。江戸時代に行ったような気分になる。
源内の序文のあるのじゃないけど、「吉原細見」は私も数冊持ってるのよね。授業で学生に見せもしていた。でもいつからか見つからなくて、書庫のどっかにまぎれこんでるんだろう。探してみて、めでたく見つかったら、また画像をお見せします。